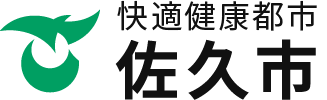人権施策
更新日:2019年2月14日
佐久市部落差別撤廃と人権擁護に関する条例
部落差別とあらゆる差別をなくし平和で差別のない明るい佐久市の実現のために制定されました。
○佐久市部落差別撤廃と人権擁護に関する条例
平成17年4月1日条例第99号
(目的)
第1条
この条例は、国民にすべての基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言の趣旨を基本理念とし、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、人権の擁護を図り、もって平和で差別のない明るい佐久市の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条
市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条
すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条
市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
(実態調査等の実施)
第5条
市は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査等を行うものとする。
(啓発活動の充実)
第6条
市は、市民の人権意識の向上を図るため、啓発媒体の活用、人権啓発指導者の育成及び人権関係団体等との協力関係の強化など、きめ細やかな啓発事業の取組と啓発組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。
(推進体制の充実)
第7条
市は、施策を効果的に推進するため、国及び県並びに関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第8条
部落差別をはじめ、あらゆる差別撤廃と人権擁護に関する重要事項について調査審議する機関として、佐久市部落差別撤廃人権擁護審議会(次項において「審議会」という。)を置く。
2
審議会の組織及び運営等に関する事項は、市長が別に定める。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
人権同和施策実施方針
1.基本的事項
人権同和問題は、人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、同時に日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる国民的課題であって、この早急な解決は、国及び地方公共団体の責務です。これまで日本国憲法に基づいて、人権に関する諸制度の整備や条約への加入など、人権に関する様々な施策が講じられてきました。
本市では、33年間にわたる同和対策事業特別措置法のもと、住まい・周辺整備など環境面においては一定の成果を見ることができました。また、市民の人権同和問題に対する理解も、人権尊重意識の普及・高揚、及び各種啓発施策等の実施により進んできています。
しかし、結婚や就職に対しての身元調査や、差別落書き、インターネット上での差別表示等、深刻で陰湿な人権侵害につながる行為が今なお発生しており、今後も取り組むべき多くの課題が残る中で、同和問題の完全解決を目指す同和行政を「部落差別をはじめあらゆる差別をなくすこと」を総合政策の原点として位置付け、すべての市民の人権が保障され、たくましく心豊かで人間性ある佐久市を築くため平成18年3月23日「部落解放都市宣言」をしました。
平成14年3月末日をもって「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特定措置に関する法律」が失効し、同和行政は特別対策から一般対策に移行されましたが、今後も「佐久市部落差別撤廃と人権擁護に関する条例」に基づき「人権教育・啓発に関する基本計画」「長野県人権教育・啓発推進指針」などと連携を図りながら、市民の人権意識の高揚・人権教育の推進に努め、一人ひとりの人権が尊重され明るく住みよい佐久市を目指します。
2.重点事項
(1)市民の人権尊重意識の普及・高揚
人権同和問題を解決するためには、市民一人ひとりが人権同和問題を自らの問題として受けとめ、差別意識をなくし、差別を怒り、差別を許さない姿勢を確立するとともに、差別をなくすための実践をしていくことが重要です。
平成19年度を初年度とする「佐久市部落差別撤廃と人権擁護に関する総合計画」を策定し、市民・学校・行政等が一体となった人権尊重のまちづくりを推進するため、人権同和教育や各種の研修会、及び啓発活動を計画的かつ積極的に推進し、市民の部落差別をはじめとするあらゆる差別問題に対する正しい理解と認識を高め、人権尊重意識の高揚に努めます。
(2)人権同和教育の推進
「人権同和教育基本方針」に沿って、基本的人権を尊重し、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくす意欲と実践力をもった人間の育成を目指して、学校教育及び社会教育相互の連携を図りながら、地域ぐるみの人権同和教育を推進します。
(3)隣保館活動
隣保館では、差別や偏見のない明るい社会づくりを目指して、地域福祉の向上や人権啓発面からの住民交流の拠点となるよう、開かれたコミュニティーセンターとして人権関係団体や周辺住民等の利用の促進を図ります。また、生活上の各種相談事業や同和問題をはじめあらゆる人権問題の解決に向けて総合的な事業の推進に努めます。
(4)住宅新築資金等貸付金の償還の推進
住宅新築資金等貸付事業の返済については、利用者の事業不振や高齢化、相続の複雑さなどに伴い、継続的な返済が困難になるケースがあるため、「佐久市住宅新築資金等貸付金未償還者調査検討委員会」において生活の状況を把握し、他の関係部課との連携を密にしながら、継続的に滞納者と連絡をとり確実な返済計画を立て返済意識を高める一方で、連帯保証人にも債務の履行を促し、あらゆる手段をとりながら滞納額の減少に努めます。
人権同和教育基本方針
1.基本方針
人権同和教育の基本理念は、人権尊重、自由、平等の精神に徹し、部落差別をなくすことを中心的課題として、あらゆる差別の解消に取組む意欲と能力を持つ人間を育てることにあり、差別に気づき、差別を許さない、真に民主的な人間形成をすることにあります。
日本国憲法が、すべての国民は法のもとに平等であり、基本的人権は侵すことができない永久の権利として保障しているにもかかわらず、今日においても部落差別が現存し、現在なお、同和地区住民は著しく基本的人権が侵害され、市民的権利と自由が多くの場面で侵されています。
市民一人ひとりが人権同和問題を自分自身の課題としてとらえ、互いの人権を尊重する意識や態度を身につけ、日常生活の中で人権尊重を当たり前のこととして、行動することにより差別のない明るい社会が実現します。
本市においても、同和問題解決のため、同和対策事業、人権同和教育の徹底を目指して歩みを進めてまいりました。
しかし、今日なお幾多の問題が現存しています。
ことに最近における幾つかの差別事象は、旧来の偏見と無理解が重なり差別を生む諸要因が取り除かれないまま残っているという現状です。この問題の早急な解決は、行政の責任であることはもちろん市民共通の課題であり、あらゆる力を結集してこそ実現されるものであります。その解決の根底をなすものは教育であります。
佐久市教育委員会は、日本国憲法と教育基本法の精神を踏まえ、教育の主体性と責任において、総合的、計画的な施策を講じ抜本的な解決を図ることを目指して、その基本方針を次のとおり定めます。
(1)学校人権同和教育においては、すべての教育活動において、生活の中にある人権、差別の問題を正しく認識させ、差別を許さない人権尊重の教育を発達段階に応じて、教育計画の中に明確に位置づけてその実施にあたります。
特に、同和地区の児童、生徒の学力向上や進路指導の徹底を図り、進学、就職の機会均等を保障するよう努めます。
(2)社会人権同和教育においては、すべての家庭、職場、地域社会において部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすために人権同和教育を推進し、部落差別の現実を認識し、差別を許さない民主的な地域づくりを目指す自主的、組織的活動の育成に努めます。特に同和地区住民の自立意識を高め、文化水準を向上させるよう諸条件の整備を図り、市民権利と自由の保障に努めます。
2.社会人権同和教育
A目標
(1)社会人権同和教育においては、人権意識の高揚を図り、すべての市民が人権尊重に徹した基本理念を踏まえ、自らの問題として部落差別の撤廃をはじめあらゆる差別をなくすために、関係機関及び関係諸団体との連携を密にして実践的教育活動を推進します。
(2)社会人権同和教育の地域拠点施設として、同和対策集会所の管理及び運営に努めます。
B実施方策
(1)推進体制の確立と関係機関の連携
佐久市人権同和教育推進協議会を中心として、総合的な推進体制の充実強化を図るとともに行政関係、教育関係各機関及び関係諸団体等の有機的な連携体制を確立します。
(2)施設の整備
同和対策集会所の管理運営の適正を図ります。
(3)指導者の研修と確保
社会教育機関及び関係諸団体等の指導者の確保と資質の向上を図るために、研修の機会を拡充します。
(4)地域における人権同和教育活動の推進
イ
差別を許さない民主的な地域づくりを目指すため、各区、女性団体、地域公民館、PTA等の諸団体と連携協力のもとに、地域ぐるみの推進体制を確立します。
ロ
市民一人ひとりが部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすことを自己の問題、地域の課題として取り組むため、公民館等を推進母体として計画的に講演会、研修会、学級講座等を開催します。
ハ
地域の人権同和教育を推進するため、人権同和教育推進員を委嘱し、指導者としての資質を高めるとともに、市内各地区を巡回指導し、差別意識の解消を図ります。
(5)解放子ども会の開催
学校・行政機関・関係運動団体・地域・保護者等の連携と浅科人権文化センター・望月人権文化センターの協力を得て同和地区児童生徒の学力向上及び、解放意識の高揚を図ります。
(6)同和地区住民の教育活動の促進
地区住民の解放への自覚を高め、社会的資質の向上を図るため学習及び教育活動の促進を図ります。
(7)職場における人権同和教育活動の育成
佐久市企業人権同和教育推進連絡協議会を中心として企業内人権同和教育を推進し、差別のない明るい職場づくりを図ります。
(8)啓発活動の推進
すべての市民を対象として人権同和教育の徹底を図るため、広報紙等を通じて計画的な啓発活動を促進します。
3.学校人権同和教育
A目標
(1)学校における人権同和教育は、基本的人権を尊重し、現代社会に根強く存在する部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすことを目指します。
(2)学校内の人権同和教育推進の体制を確立するとともに諸条件の整備を図ります。
(3)同和地区児童、生徒等の学力の向上や進路指導の徹底と就学・進学に努めます。
B実施方策
(1)人権同和教育推進体制の強化
イ
市内のすべての教職員が人権同和問題について正しい認識を持ち、一貫した人権同和教育指導体制の確立に努めます。
ロ
人権同和教育をあらゆる教育活動に位置づけ、児童生徒の正しい判断力と実践力、差別を許さない心情や意志をもった人間性を育てます。
(2)人権同和教育指導者の確保と研修の充実
教職員の研修の機会とその充実を図ります。
同和問題について
日本社会の歴史的過程で形づくられた身分的差別によって、国民の一部の人々が長い間、職業や住まい、結婚、交際、服装などを制限されるなどの差別を受けていました。明治4年(1871年)の解放令により制度上の身分差別はなくなりましたが、特定の地域出身であることやそこに住んでいることを理由に、人権が侵害されることが同和問題です。
この問題を解決するために、昭和44年(1969年)に「同和対策事業特別措置法(同対法)」が制定されて以来、国や地方公共団体による特別対策として、生活・住環境整備、産業・就労対策、差別意識解消のための教育・啓発などが行われてきました。その結果、住環境整備などでは大きく改善されたことから、平成14年(2002年)3月に特別対策は終了しました。しかし、一方で身元調査や結婚・就職差別などの心理的差別は、いまだに解消されていません。
同和問題は、これらの人々が、今なお結婚を妨げられたり、就職で不公平に扱われたり、その他日常生活の上でいろいろな差別を受けるという、重大な人権問題です。
この問題の解決には、国民一人ひとりが同和問題について、一層理解を深め、自らの意識を見つめ直すとともに、自らを啓発していくことが必要です。
犯罪被害者やその家族の人権
犯罪被害者等とは
犯罪被害者等とは、犯罪や犯罪と同様な有害な行為によって、心身に害を被った方やその家族・遺族をいいます。無差別殺人などの凶悪犯罪や、窃盗、交通事故などの犯罪で、誰もが被害者やその家族となる可能性があります。そして、被害にあった多くの方が、犯罪の直接的な被害だけでなく、被害後の精神的ショックや経済的負担などさまざまな困難に直面し、苦しんでいる状況にあります。
私たちは、ある日突然、本人の意思とは無関係に、命を奪われる、けがをする、物を盗まれるなどの生命、身体、財産上の被害を受ける可能性があります。さらに、犯罪等にあうと、こうした直接的な被害だけでなく、被害後に生じるさまざまな問題(二次的被害)にも苦しめられることになります。
二次的被害とは
- 事件に遭ったことによる精神的ショックや身体の不調
- 医療費の負担や失職、転職などによる経済的困窮
- 捜査や裁判の過程における精神的、時間的負担
- 周囲の人々の無責任なうわさ話やマスコミの行き過ぎた取材・報道によるストレス
などによる被害のことです。
犯罪被害者とその家族の人権について考えましょう
周りの人は、被害者の気持ちをあたたかく受け止めて接し、責めたり、無理に励ましたりすることなど避けていただくことが大切です。また、興味本位のうわさ話をすることはやめましょう。被害者の方の心の傷の回復には、周囲の人々の理解と支持が必要です。
国・県の取り組み
犯罪被害者の権利利益の保護を図るため、長野県においても、県・県警・関係機関などが連携してさまざまな支援策を行っています。国・長野県における取組などについては、次のホームページをご覧ください
佐久市における取組
佐久市における犯罪被害者等支援に関わる各種相談窓口
| 区分 | 業務(支援)内容 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 犯罪被害者等支援担当窓口 |
|
人権同和課 | 0267-62-3135 |
| 女性 |
|
福祉課 | 0267-62-3147 |
| 少年 |
|
子育て支援課 | 0267-62-3149 |
| 学校 |
|
学校教育課 | 0267-62-3478 |
| 福祉 |
|
福祉課 | 0267-62-3147 |
| 高齢者 |
|
高齢者福祉課 | 0267-62-3157 |
| 保健・医療 |
|
健康づくり推進課 | 0267-62-3189 |
| 住居 |
|
長野県住宅供給公社 |
0267-78-5410 |
「長野犯罪被害者支援センター」による支援
犯罪被害者等の悩みや精神的被害についての電話相談を「長野犯罪被害者支援センター」で行っています。専門的な研修を受けた相談員が電話を受けていますので、安心してご相談ください。相談は無料です。
| 長野犯罪被害者支援センター(長野市) | |
|---|---|
| 電話番号 | 026-233-7830 |
| 相談日 | 平日10時~16時 |
- [
 長野犯罪被害者支援センター(外部サイト)]とは、平成11年6月から支援事業を開始した特定非営利活動法人(NPO)です。犯罪被害者等の相談、広報啓発、「犯罪被害者等給付金」の申請補助などを行って犯罪被害者等の支援をしています。
長野犯罪被害者支援センター(外部サイト)]とは、平成11年6月から支援事業を開始した特定非営利活動法人(NPO)です。犯罪被害者等の相談、広報啓発、「犯罪被害者等給付金」の申請補助などを行って犯罪被害者等の支援をしています。 - 「
 日本司法支援センター(法テラス(外部サイト))」についても、法制度の紹介、犯罪支援窓口の紹介、弁護士の紹介等犯罪被害者に対する支援を行っています。
日本司法支援センター(法テラス(外部サイト))」についても、法制度の紹介、犯罪支援窓口の紹介、弁護士の紹介等犯罪被害者に対する支援を行っています。