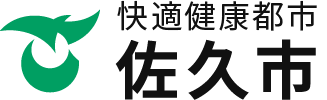「自然観察会」を実施!
更新日:2025年2月5日
佐久市では、生きものたちとふれあい、自然環境について考えるきっかけとしていただくため、自然観察会を実施しています。
以下に過去に実施した観察会の様子をご紹介します。
令和6年度自然観察会の様子
鹿革のクラフト体験講座
 シカについてのお話
シカについてのお話
 鹿革の材料
鹿革の材料
 製作体験中
製作体験中
今回の観察会は、室内でクラフト体験を行いました。
鹿革を使って、クラフト体験を実施し、シカの生態や佐久の自然環境について考える機会を設けました。
前半は、シカが市内の森林内にどういった影響を及ぼしているのか等のお話をしていただきました。
山菜を採りに普段から山に入っている人もいれば、なかなかそういった機会がない人もいて、それぞれの立場で聞き入っていました。
後半は、鹿革を使った製作体験を実施し、大人はキーホルダー作り、子どもはストラップを作りました。
鹿革を2本選び、それを編み込んでいく作業が難しく、講師の先生に直接やり方を聞きながら、完成させていた姿が印象的でした。
みなさん熱心に手を動かし、手仕事の大事さを感じつつ、市内の自然環境に目を向けるきっかけになれば幸いです。
- 日 時:令和7年2月2日(日曜)
- 場 所:市民創錬センター
- 参加者:大人13名、子ども3名、計16名
- 講 師:池田 好見 氏
冬の野鳥観察会
 野鳥の説明中
野鳥の説明中
 望遠鏡や双眼鏡で観察中(1)
望遠鏡や双眼鏡で観察中(1)
 望遠鏡や双眼鏡で観察中(2)
望遠鏡や双眼鏡で観察中(2)
今回の観察会は、野の鳥の丘公園(杉の木貯水池)で行いました。
天候にも恵まれ、温かい日差しの中観察会を実施することができました。
観察会では、マガモ、カワウ、オオサギ、トビをはじめ、キンクロハジロも見られました。
長野県の準絶滅危惧種カンムリカイツブリも確認でき、さらに、今年は雛が孵り、幼鳥のカンムリカイツブリの姿も見ることができました。
長野県の絶滅危惧種であるハヤブサ、「飛ぶ宝石」と言われているカワセミなど、珍しい野鳥を観察できた参加者の方もいらっしゃいました。
今年は例年に比べてそこまで寒くないようで、貯水池に滞在している野鳥の数は少ないとのことです。
これから段々と寒くなるに連れて、北の方から渡ってくる鳥たちが、貯水池に集まってくるようです。
- 日 時:令和6年12月1日(日曜)
- 場 所:野の鳥の丘公園(杉の木貯水池)
- 参加者:大人20名、子ども6名、計26名
- 講 師:木内 清 氏(日本鳥学会会員)
依田 昌晃 氏(東信自然史研究会)
カブトムシの幼虫観察会
 館内で説明
館内で説明
 腐葉土の山
腐葉土の山
 幼虫掘り出し体験
幼虫掘り出し体験
 カブトムシの幼虫
カブトムシの幼虫
今回の観察会は、昆虫体験学習館周辺で行いました。
この観察会は、毎年大変好評で、すぐに予約でいっぱいになります。
みなさんこの日を楽しみに待っていたようで、案内のとおり、「飼育ケース」を持参で来場されました。
館内での説明もそこそこに、カブトムシの幼虫を育てている腐葉土の山へと移動し、幼虫を掘り出す体験を実施しました。
みなさんはじめは恐る恐る土を掘り返していましたが、カブトムシの幼虫が土の中から見つかるたびに、大胆に掘り起こし、観察会の最後の方では、手が真っ黒になっていました。
参加者には、自分で掘り出したカブトムシの幼虫をプレゼントしていただきました。
カブトムシの幼虫は腐葉土中で越冬し、個体にもよりますが、だいたい次の年の5月~6月頃に成虫になるそうです。
講師の先生からは、カブトムシの幼虫の飼育方法をいろいろ教えていただき、大変盛り上がりました。
- 日 時:令和6年10月27日(日曜)
- 場 所:昆虫体験学習館周辺
- 参加者:大人9名、子ども9名、計18名
- 講 師:渡辺 衛 氏(昆虫体験学習館)
秋の植物観察会
 登山中
登山中
 植物の説明中
植物の説明中
 展望櫓からの眺め
展望櫓からの眺め
今回の観察会は、虚空蔵山で行いました。
集合時点では小雨が降っていましたが、開始時刻には雨もあがり晴れ間も見られました。
虚空蔵山の山頂へはいくつか登山コースがあり、今回は多福寺からの石仏コースから登っていきました。
登り始めると、登山道にはツリフネソウやトリカブト、毒キノコなどさまざまな植物がみられ、講師の先生が足を止め、説明を聞き、また山を登るというように進んでいきました。
また、山の斜面には多くの石仏が置かれ、全部で88体あるそうです。
山頂には佐久平を一望できる展望櫓があり、標高773.6メートルの虚空蔵山から雄大な景色を見ることができました。
今回虚空蔵山にはじめて登るという参加者がほとんどで、地元に身近な自然があることを知っていただく良い機会になりました。
- 日 時:令和6年9月29日(日曜)
- 場 所:虚空蔵山
- 参加者:大人16名、子ども1名、計17名
- 講 師:佐藤 文一 氏(ハンノキ会 会長)
セミの抜け殻を探そう
 抜け殻探し
抜け殻探し
 標本の説明中
標本の説明中
 抜け殻の分類作業
抜け殻の分類作業
今回の観察会は、駒場公園で行いました。
夏休み中の子どもたちが多く参加し、とても賑やかな観察会となりました。
セミの抜け殻は木の幹だけでなく、葉っぱの裏側や地面にも落ちている場合があり、参加者は公園内を注意深く散策していました。
また、珍しく羽化中のセミを見つけることができ、みなさんと一緒に観察することができました。
講師の先生から、公園内は日影が多く少し薄暗いため、夜と間違えたセミの幼虫がお昼間に羽化しているのだろうという話もありました。
抜け殻の分類の仕方も教えていただき、虫眼鏡で真剣に観察している姿が見られました。
最も多かった種類は、アブラゼミで485匹、観察会全体では689匹のセミの抜け殻を見つけることができました。
- 日 時:令和6年8月8日(木曜)
- 場 所:駒場公園 及び 佐久市立近代美術館視聴覚室
- 参加者:大人8名、子ども16名、計24名
- 講 師:浜田 崇 氏(長野県環境保全研究所)
栗林 正俊 氏(長野県環境保全研究所)
川の生きもの観察会
 中佐都橋からの様子
中佐都橋からの様子
 生きものの説明中
生きものの説明中
 観察会の様子
観察会の様子
今回の観察会は、中佐都橋下の湯川で行いました。
夏休みに入ったこともあり、子どもたちとさまざまな川の生きものを観察することができました。
川に入ると、水深の浅い場所や深い場所、流れの速い場所や遅い場所があり、みなさん慎重に歩いていました。
水温はちょうど良く、夏の暑さが足元から少しだけ和らぐ感覚でした。
川の中で網を使って、ハヤ等の魚のほか、エビやヘビトンボ、トビケラ等を捕まえることができました。
捕まえた生きものの名前が分からない場合は、講師の先生に聞きに行く姿も見られました。
大人も子どもも、楽しく観察することができました。
- 日 時:令和6年7月26日(金曜)
- 場 所:中佐都橋下の湯川
- 参加者:大人8名、子ども10名、計18名
- 講 師:沼田 清 氏(信州水環境マップ・ネットワーク)
有賀 宏道 氏(長野県地球温暖化防止活動推進員)
春の野鳥観察会
 観察会の様子(1)
観察会の様子(1)
 観察会の様子(2)
観察会の様子(2)
 まとめ
まとめ
今回の観察会は、旧美笹自然観察園で行いました。
当日は天候にも恵まれ、十数種類の野鳥を観察することができました。
園内を散策すると、サンショウクイの「ピリリ、ピリリ」という鳴き声や、ジョウビタキの美しい姿が見られました。
野鳥の鳴き声は聞こえるのですが、実際に双眼鏡で姿を見つけるのが難しかったです。
自然の中で耳を澄ませると、さまざまな音が聴こえてきます。
「水の流れる音」、「風で木々が揺れる音」、「土を踏みしめる音」など、普段気にしない音がとても新鮮でした。
講師の先生の解説を聞きながら、あっという間の2時間30分でした。
- 日 時:令和6年5月11日(土曜)
- 場 所:旧美笹自然観察園
- 参加者:大人17名、子ども4名、計21名
- 講 師:木内 清 氏(日本鳥学会会員)
依田 昌晃 氏(東信自然史研究会)
令和5年度自然観察会の様子
神社林で自然を観察しよう
観察会の様子(1)
観察会の様子(2)
イチョウ(メス)
今回の観察会は、平賀神社で行いました。
境内を散策しながら、そこにある樹木や草花、野鳥などの性質や人の暮らしとの関係などを教えていただきました。
例えば、イチョウには雌雄があって、実をつけるかどうかで判別できるほか、葉の形が扇型であればメス、真ん中に切れ込みが入っていればオスなのだそうです。
また、しばしば神社に植樹されている榧(カヤ)は、昔は枝葉を燻して蚊を追い払うことに使われていたそうです。
見慣れている動植物でも新しく知ることが多くあり、身近な自然に興味を持つきっかけになりました。
日時:令和6年1月24日(水曜日)
場所:平賀神社
参加者:大人7名
講師:篠澤 明剛氏
冬の野鳥観察会
 説明の様子
説明の様子
 観察会の様子
観察会の様子
 池の野鳥
池の野鳥
今回の観察会は、杉の木貯水池(野の鳥の丘公園)で行いました。
ハシビロガモやシラサギ、カワウなどおよそ14種類の野鳥を観察することができました。
私たちにも馴染みのあるカモの仲間が多く見られましたが、それぞれの骨格の違いや捕食の特徴などを先生に教えていただき、新しい発見があった観察会になったと思います。
また、環境の変化により絶滅の危機に瀕している種もいることを聞く中で、これからの生活や自然との関わり方についても考えていくきっかけになりました。
日時:令和5年11月18日(土曜日)
場所:杉の木貯水池(野の鳥の丘公園)
参加者:大人12名、子ども4名、計16名
講師:木内 清氏(日本鳥学会会員)
依田 昌晃氏(東信自然史研究会)
カブトムシの幼虫観察会
説明の様子
幼虫探し
幼虫発見
今回の観察会は、パラダ昆虫体験学習館で行いました。
館内では、カブトムシの特徴や成長過程、飼育方法などを教えていただきました。カブトムシの寿命は約1年で、その中でも幼虫の期間は約9か月と最も長く、飼育にあたっては幼虫にとって快適な空間を維持してあげることがとても重要なのだそうです。
実際に幼虫を腐葉土の中から掘り出した際には、子どもたちから大きな歓声が上がっていました。幼虫をよく観察すると、オスかメスかが判別できることも教えていただき、採取した幼虫がどちらなのかじっくり観察していました。
大切にカブトムシを育てる中で、昆虫や自然環境により興味をもっていただければと思います。
日時:令和5年10月21日(土曜日)
場所:パラダ昆虫体験学習館(平尾山公園内)
参加者:大人10名、子ども11名、計21名
講師:パラダ昆虫体験学習館 渡辺 衛氏
秋の植物観察会
 観察会の様子(1)
観察会の様子(1)
 観察会の様子(2)
観察会の様子(2)
 サラシナショウマ
サラシナショウマ
今回の観察会は旧美笹自然観察園で行いました。
講師の先生によると、旧美笹自然観察園では年間で約550種類の植物が見られるなか、今回は40種類程度が確認できました。
落葉樹林内の木陰に自生することが多いサラシナショウマは、小さな白い花が集まって穂状に咲いており、近づくと優しい甘い香りがしました。
また、葉が開くとモミジ葉の形に似ているモミジガサは、春には旬を迎える山菜であることなどを教えていただきました。
見慣れない植物からタンポポなどの身近な植物まで、その興味深い特徴や私たちの生活への関わり方などを知り、違う季節にもまた訪れたい気持ちになる観察会となりました。
日時:令和5年9月23日(土曜日)
場所:旧美笹自然観察園
参加者:大人7名、子ども3名、計10名
講師:佐藤 文一氏
川の生きもの観察会
観察会の様子
採取した生きもの
 説明の様子
説明の様子
今回は、佐久市根々井の湯川で川の生きものを観察しました。
ハヤなどの魚や、ヌマエビ、カゲロウの幼虫、トビケラの幼虫などを観察することができました。
見たことのない生きものは図鑑などで調べ、それぞれに発見がある時間となりました。
講師の先生からは、川の水がきれいなのかそうでないかによって、住む生きものも変化していくことを教えていただきました。
それが私たちの生活にも影響してくることを知り、最後に全員でごみ拾いをしました。
これからも、豊かな河川環境が持続できるよう、自然を大切にしていきたいですね。
期日:令和5年7月28日(金曜日)
場所:佐久市根々井(湯川)
参加者:大人9名、子ども13名、計22名
講師:沼田 清氏(信州水環境マップ・ネットワーク事務局)
有賀 宏道氏(長野県地球温暖化防止活動推進員)
春の野鳥観察会
 観察会の様子(1)
観察会の様子(1)
 観察会の様子(2)
観察会の様子(2)
 観察会の様子(3)
観察会の様子(3)
今回の観察会は、旧美笹自然観察園で行いました。
当日は天気にも恵まれ、爽やかな新緑の中、二十数種類の野鳥を観察することができました。
シジュウカラ科の鳥たちが多く、子育て中の巣の様子を見ることもできました。
普段何気なく聞いている鳥の鳴き声も、先生の解説を聞きながら実際に双眼鏡で見つけることが
できると新しい感動があります。
野鳥の鳴き声に癒されながら園内を散策する中で、野鳥の以外の動植物の生態についても知ることができ、
環境保全についても考えてみるきっかけになったと思います。
日時:令和5年5月21日(日曜日)
場所:旧美笹自然観察園
参加者:大人17名、子ども5名、計22名
講師:木内 清氏(日本鳥学会会員)
依田 昌晃氏(東信自然史研究会)
令和4年度自然観察会の様子
冬の野鳥観察会
 説明の様子
説明の様子
 トモエガモ
トモエガモ
 池の鳥
池の鳥
今回の観察会は、杉の木貯水池(野の鳥の丘公園)で行いました。
オオバンやマガモなどおよそ20種類の野鳥を観察することができ、トモエガモという珍しい鳥も見ることができました。
講師の先生に教えていただきながら、野鳥を通して環境にふれる良い機会となったかと思います。
身近にいる鳥を見て、「あの鳥は何だろう」と思って調べたり、これから環境について考えていくきっかけとなれば幸いです。
日時:令和4年11月19日(土曜日)
場所:杉の木貯水池(野の鳥の丘公園)
参加者:大人15名、子ども3名、計18名
講師:木内 清氏(日本鳥学会会員)
依田 昌晃氏(東信自然史研究会)
カブトムシの幼虫観察会を実施しました!
 説明の様子
説明の様子
 カブトムシの幼虫探し
カブトムシの幼虫探し
 幼虫
幼虫
今回の観察会はパラダ昆虫体験学習館で行いました。
講師の先生からは、カブトムシの特徴や、カブトムシの成長過程のお話、また実際に幼虫を育てる際のポイントを説明していただきました。
参加者は説明をしっかりと聞き、餌を与える頻度や、飼育する場所など、育て方について質問をしていました。
幼虫を掘り出す作業についても、皆さん楽しそうに探していて、見つけた際には喜びの声が上がっていました。
来年立派なカブトムシに成長すると良いですね。
日時:令和4年10月15日(土曜日) 午前10時から正午
場所:パラダ昆虫体験学習館(平尾山公園内)
参加者:大人7名、子ども14名 計21名
講師:昆虫体験学習館 館長 金子 順一郎氏
秋の植物観察会を実施しました!
観察会の様子(1)
観察会の様子(2)
観察会の様子(3)
今回の観察会は稲荷山公園で行いました。
講師の先生からは公園内の様々な植物について、名前や特徴、私たちの生活にどのように関わっているかなどを解説いただきました。
ハルジオンとヒメジョオンは茎の中が空洞かどうかで見分けられることや、コナラとクヌギのどんぐりの違いなど、身近な植物について教えていただきました。
当日は天気も良く、秋らしい爽やかな気候の中、たくさんの植物を観察することができました。
日時:令和4年9月17日(土曜日)
場所:稲荷山公園
参加者:大人9名
講師:佐藤 文一氏
令和3年度自然観察会の様子
冬の野鳥観察会を実施しました!
 観察会の様子
観察会の様子
 双眼鏡を使って観察
双眼鏡を使って観察
望遠鏡を使って観察
当日は雪がちらつく場面もありましたが、様々な野鳥を観察することができました。
身近で見かけるカモにも種類がたくさんあり、オスとメスで姿がまったく違っていたり、水中に潜るカモ、潜らないカモがいたりと、その違いについて双眼鏡をのぞきながら興味深く観察していました。
野鳥の生態について解説を聞きながらメモや質問をしたり、講師の望遠鏡をのぞいて鳥の細部まで観察したりと、身近な自然に目を向けながら貴重な体験ができたかと思います。
様々な野鳥がいるこの環境を今後も守っていきたいですね。
日時:11月27日(土曜日) 午前10時から正午まで
場所:杉の木貯水池(野の鳥の丘公園)
参加者:大人12名、子ども2名、計14名
講師:木内 清氏(日本鳥学会会員)、依田 昌晃氏(東信自然史研究会)
令和元年度自然観察会の様子
冬の星空観察会を実施しました!
観察会の様子
 天体望遠鏡の説明
天体望遠鏡の説明
 星座のお話し
星座のお話し
今回の観察会はうすだスタードームで行いました。
講師の先生からは、太陽の大きさを1cm程度の丸い玉に例えてお話しいただき、宇宙の広さを楽しく学ぶことができました。
当日は雲が多く、あまり天体を見ることができませんでしたが、ふたご座の星の一つである「カストル」という星を観察することができました。
また、プロジェクターを使って様々な星座や星雲のお話を聞くことができました。
星の観測には、光害(街の明かりなどによって夜空が明るくなってしまう公害)や、気候の状況など、環境の変化と密接な関係にあるということを教えていただきました。
これからも、きれいな星空を見ることができるよう、一人ひとりが自然環境に目を向け、守り続けていきたいですね。
日時:令和2年1月25日(土曜日)午後6:30から8:30まで
場所:うすだスタードーム
参加者:大人13名、子供12名、計25名
講師:うすだスタードーム 職員 坪根 徹氏
カブトムシの幼虫観察会を実施しました!
観察会の様子
メモを取る子供
幼虫を掘りに向かいます
幼虫を取ることができました!
今回の観察会はパラダ昆虫体験学習館で行いました。
講師の先生からはいろいろなカブトムシの特徴やカブトムシの幼虫が成虫になるまでのお話をしていただいたり、クイズ形式で昆虫の体の特徴などについて教えていただいたりしました。
子供たちは熱心にメモを取ったり、元気に手を挙げたりと、とても積極的に参加していました。
講師の先生のお話の後はカブトムシドームまで向かい、カブトムシの幼虫を腐葉土の山から掘り出しました。
子供たちは「みつけた!」、「大きい!」と皆さん大変喜んでいる様子でした。
昆虫館へ戻り、講師の先生からカブトムシの育て方を教わり、観察会を終了しました。
カブトムシを育てる中で、命の大切さや昆虫たちが生きる自然環境を大切にする気持ちを持っていただけたら幸いです。
日時:令和元年10月5日(土曜日)午前10:00から正午まで
場所:パラダ昆虫体験学習館(平尾山公園内)
参加者:大人22名、子供11名、計33名
講師:昆虫体験学習館 館長 金子 順一郎氏
秋の植物観察会を実施しました!
植物の説明
観察会の様子
今回の観察会は、市街地からも近い虚空蔵山で行いました。
講師の先生からは、およそ50種類の植物について、名前の由来や、特徴、有用性などを解説していただきました。
シロツメクサ(クローバー)は、オランダからガラス器具を運ぶ際に、緩衝材として詰められていた草であったため、シロツメクサ(白詰め草)と呼ぶことを教えていただきました。
参加者の方からは、また参加したい、もっと長い時間やってほしい、普段は目に入っても見過ごしてしまっている植物について知ることができてよかった、等々、喜んでいただきました。
観察会を通して、植物やそれらが構成する自然環境を大切にする気持ちを持っていただけたら幸いです。
日時:令和元年9月26日(木曜日)午前9:00から正午まで
場所:虚空蔵山(佐久市根岸)
参加者:大人14名
講師:中山 洌氏
川の生きもの観察会を実施しました!
川の生きものの説明
観察会の様子
採取したサワガニ
今回は千曲川の支流で川の生きものを観察しました。
ハヤ(ウグイ)やドジョウなどの魚や、サワガニ、ナガレトビケラやコオニヤンマの幼虫などを観察することができました。
ほかにも、ヤツメウナギやシマドジョウといった大変珍しい魚も見ることができました。
講師の先生からは、川の水がきれいなのかそうでないかによって、川に住む生きものも変化していくことを教えていただきました。
参加者の皆さんで捕まえた生きものを見てみると、きれいな川であることが分かりました。
これからも、生きものが多く住む豊かな河川環境が持続できますよう、自然を大切にしていきたいですね。
日時:令和元年7月26日(金曜日)午前10:00から正午まで
場所:千曲川スポーツ交流広場
参加者:大人11名、子供20名、計31名
講師:篠澤 明剛氏、沼田 清氏
山野草を探してみようを実施しました!
観察会の様子
山野草についての説明
当日は、平賀神社を散策しながら山野草の観察を行いました。
ハナミズキやヤマボウシ、ツツジ、マユミ、ウルシ、ナルコユリなど、およそ30種類に及ぶ植物について、その特徴や名前の由来、分布、使用用途などを教えてもらいました。
また、「かて飯」という、お米と一緒に炊いて食べられていた山野草があることを教えてもらいました。
参加者の方からは、「ヒノキは火が起きやすいため、火の木(ヒノキ)と呼ぶ説があることや、フジは地面に伏すように生えるため伏地(フジ)と呼ぶ説があるなど、名前の由来を教えてもらい、大変良かった。」、「植物だけでなく、周辺に生息する生き物や環境についても話を聞けてよかった。」と、大変喜ばれました。
身近な自然が続くよう、これからも自然環境を守っていきたいですね。
日時:令和元年5月30日(木曜日)午前9:30から11:00まで
場所:平賀神社(佐久城山小学校近く)
参加者:大人5名
講師:篠澤 明剛氏(自然観察インストラクター)
バードウォッチングを楽しもうを実施しました!
旧美笹自然観察園を散策
野鳥観察の様子
オオルリ
コサメビタキ
当日は天気にも恵まれ、多くの野鳥を観察することができました。
オオルリやキビタキなどが見られたり、コサメビタキの求愛する様子を見ることができました。
双眼鏡で野鳥を見つけるのはなかなか難しいですが、その分、見つけることができた時の感動はひとしおです!
自然の中で野鳥の声に耳を澄ませたり、野鳥の生態について解説を聞きながら園内を散策したりすることで、
バードウォッチングを楽しめたのではないでしょうか。
これからも、こうした自然を守っていきたいですね。
日時:令和元年5月11日(土曜日)午前8:00から10:30まで
場所:旧美笹自然観察園(佐久市前山)
参加者:大人17名、子供5名、計22名
講師:木内 清氏(日本鳥学会会員)、依田 昌晃氏(東信自然史研究会)、木内 賢治氏(ボランティア)
平成30年度自然観察会様子
冬の星空観察会を実施しました!
星についての説明を受けました
天体望遠鏡の仕組みを学びました
星座を確認しました
今回は、うすだスタードームで「冬の星空観察会」を実施しました。
美しい星空を観察する方法や冬に確認できる星座などについてスライドを使って説明していただきました。
太陽を1センチ程度の玉に見立てて、宇宙の規模についても学ぶことができました。
観察会開始当初はくもり空でしたが、だんだんと晴れ、最後は天体望遠鏡を使って星空を観察することができました。
美しい星空を見ることができる自然環境をこれからも保っていきたいですね。
日時:平成31年1月26日(土曜日)午後6時から午後8時まで
場所:うすだスタードーム
参加者:12名
講師:坪根 徹氏(うすだスタードーム職員)
カブトムシの幼虫観察会を実施しました!
カブトムシの生態について学ぶ様子
カブトムシドームへ向かいます
幼虫を見つけることができました
今回は、パラダにある昆虫体験学習館で「カブトムシの幼虫観察会」を実施しました。
クイズを交えながらカブトムシやトンボなどの昆虫について学びました。
その後は、カブトムシドームまで行き、幼虫堀りを行いました。前日まで雨が降り続いたこともあり、幼虫は地表近くまで出てきていたため簡単に見つけることができました。
最後に金子館長さんから「小さくても命には変わりありません、最後まで大切に育てましょう」というお話をいただきました。
来年、元気に成虫になる姿を楽しみに育てていきたいですね!
日時:平成30年10月13日(土曜日)午前10時から正午まで
場所:パラダ昆虫体験学習館
参加者:34名
講師:金子 順一郎氏(昆虫体験学習館館長)
秋の植物観察会を実施しました!
 観察会の様子1
観察会の様子1
 観察会の様子2
観察会の様子2
 山頂からの景色
山頂からの景色
今回は、「虚空蔵山」にて秋の植物観察会を実施しました。
真夏日となった中での開催となりましたが、山道は涼しく、秋風を感じることができました。
観察会では、雑草と野草の違いや植物の見分け方などを講師の先生に説明していただき、秋の虚空蔵山で自然を堪能することができました。
身近な自然を守るためにできることを考えていきたいですね。
日時:平成30年9月6日(木曜日)午前9:00から正午まで
場所:虚空蔵山(佐久市根岸)
参加者:15名
講師:中山 洌氏(自然観察インストラクター)
川の生きもの観察会を実施しました!
川の生きものを採集する様子
採集した生きものの判別を行う様子
生息する生きものの種類を調査することで川の水質を判断することができるため、水質の調査も兼ねて身近な千曲川で「川の生きもの観察会」を実施しています。
今年はアカザやヤツメウナギなど大変珍しい生きものの観察も行うことができました。また、水質面もきれいな川であることが確認できました。これからも身近にあるきれいな川を守っていきたいですね。
日時:平成30年8月18日(土曜日)午前10:00から正午まで
場所:佐久市鳴瀬(千曲川)
参加者:22名
講師:篠澤 明剛氏(自然観察インストラクター)、沼田 清氏(信州水環境マップ・ネットワーク事務局)
植物とふれあおうを実施しました!
 観察会の様子
観察会の様子
 食べられる植物の説明
食べられる植物の説明
「植物とふれあおう」では、春にみられる植物の解説や、食べることのできる植物の見分け方について勉強しました。植物の名前の由来や生活との関わりを歴史を絡めて分かりやすく説明していただきました。
観察会の最後には、普段は食べる機会が少ないタンポポなどの植物をその場で天ぷらにする実食体験も行いましたが、身近な植物もおいしく食べることができ、参加者の方々も驚きの様子でした。
これだけおいしく食べることができると、これからは身近な植物にも興味がわいてきそうですね。
日時:平成30年6月7日(木曜日)午前10:00から正午まで
場所:平賀神社(佐久城山小学校近く)
参加者:大人13名
講師:篠澤 明剛氏(自然観察インストラクター)
バードウォッチングを楽しもうを実施しました!
 望遠鏡で鳥を探す参加者
望遠鏡で鳥を探す参加者
 鳥の巣を観察する参加者
鳥の巣を観察する参加者
センダイムシクイ
メジロ
昨年に引き続き、旧美笹自然観察園で野鳥の観察会を行いました。
センダイムシクイやメジロ、キビタキなど野鳥のほかにもサクラソウやハンノキなどの珍しい植物も観察することが出来ました。
さらに鳥の鳴き声を人の言葉に置き換えて覚えやすくする「聞きなし」という方法も教えていただきました。
これからもマナーを守りながらバードウォッチングを続けていきましょう。
日時:平成30年5月20日(日曜日)午前9:00から正午まで
場所:旧美笹自然観察園(佐久市前山)
参加者:大人22名、子供1名、計23名
講師:木内 清氏(日本鳥学会会員)、依田 昌晃氏(東信自然史研究会)、木内 賢治氏(ボランティア)
平成29年度自然観察会の様子
カブトムシの幼虫観察会を実施しました!
昆虫について学習しています。
幼虫堀りをしている様子です。
館内の見学をしました。
今回は、パラダにある昆虫体験学習館で「カブトムシの幼虫観察会」を実施しました。
まずは、昆虫体験学習館で座学を行いました。昆虫の足は何本か?昆虫の体はいくつにわかれているのか?といった昆虫の特徴をクイズ形式で学びました。子供たちは元気に金子館長の質問に答えていました!
そして、カブトムシドームまで行き、幼虫堀りを体験しました。一人一匹家に持ち帰り、育ててもらいます。みなさん真剣に幼虫を探していて、見つけた時には幼虫の大きさに驚きながらも、とても嬉しそうな表情をしていました。
昆虫体験学習館に戻り、座学でカブトムシの一生と育て方を学び、最後に館内の見学をしました。
来年の夏、立派なカブトムシに出会えるといいですね。
日時:平成29年度10月14日(土曜日)午前10時から正午まで
場所:昆虫体験学習館(パラダ)
参加者:大人9名 子供13名 計22名
講師:金子 順一郎氏(昆虫体験学習館長)
秋の植物観察会を実施しました!
今回は、佐久城山小学校の近くにある「平賀神社」を会場にして、観察会を実施しました。
「秋の植物観察会」では、秋にみられる植物の解説や、食べることのできる植物の見分け方について勉強しました。ケヤキ、サクラ、イチョウ、カエデ、マツなど普段目にしている植物を、実際に触ったり匂いを嗅いでみたりすることで新たな発見がありました。
観察会の最後には、それまで観察してきた植物の中で、食べることのできるものをその場で天ぷらにして試食してみました。参加者の皆さんには、「目も口も楽しむことができた」と観察会を楽しんでいただきました!
また、NHKの方に観察会の様子を取材していただきました!
日時:平成29年9月27日(水曜日)午前10:00から正午まで
場所:平賀神社(佐久城山小学校近く)
参加者:大人9名
講師:篠澤 明剛氏(自然観察インストラクター)
夏の植物観察会を実施しました!
今回は、はじめて「虚空蔵山」を会場にして、観察会を実施しました。
虚空蔵山は植物の種類が豊富で、観察会が始まってすぐに「この植物はなんですか?」と質問があり、立ち止まりながらじっくりと観察ができました。
曇り空の中観察会が始まりましたが、途中で大雨になり、雨宿りをしながら足元や周辺の植物について、講師の中山先生より解説をしていただきました。
参加者のみなさんは質問をしたり、写真を撮るなど貴重な経験をしていただきました。
雨の影響で、1時間早い解散となってしまいましたが、ヤマホタルブクロやアカネなど、約30種の植物を観察することができました。
日時:平成29年7月25日(火曜日) 午前9:00から10:30(雨天により1時間早く解散)
場所:虚空蔵山(佐久市伴野)
参加者:大人15名 子ども3名 計18名
講師:中山 冽氏(自然観察インストラクター)
春のバードウォッチングを実施しました!
双眼鏡で野鳥を観察
旧美笹自然観察園について学びました
オオルリ
キビタキ
 クロツグミ
クロツグミ
当日はお天気にも恵まれ、大勢の皆様にご参加をしていただきました。旧美笹自然観察園は、野鳥の観察としては初めて行われた場所でしたが、美笹の美しい自然を求めたたくさんの野鳥を観察することができました。
キビタキやクロツグミ、オオルリにサンショウクイなど、約20近くの野鳥の解説に熱心に耳を傾けていました。
また、名前の由来や、渡り鳥が海を渡るときは月の位置や星座を頼りにしているなどといった豆知識を聞くことができ、大変楽しかったとご好評をいただきました。
参加者の皆様にも貴重な経験をしていただき、充実した観察会となりました!
日時:平成29年5月14日(日曜日)
場所:旧美笹自然観察園
参加者:大人26名、子供5名、計31名
講師:木内 清氏(日本鳥学会会員)
依田 昌晃氏(東信自然史研究会)
木内 賢治氏(ボランティア)
平成28年度自然観察会の様子
野鳥観察会を実施しました!
まずは、先生から杉の木調整池で見ることができる野鳥の種類を教えてもらいました。
浮島にはたくさんの鳥たちが!!
望遠鏡を使ってじっくりと観察しました。
当日は、寒さも厳しくなく、快適にバードウォッチングを楽しむことができました!
望遠鏡の使い方や鳥の種類や生態、鳥の防寒対策や羽の仕組みについて説明を受けた後、いよいよ観察へ。
カルガモやアオサギはもちろんのこと、ミコアイサやカンムリカイツブリなど15種類の鳥を見ることができ、とても充実した観察会となりました!!
今回の会をきっかけに鳥や多くの動植物が暮らす自然について関心をよせる機会がふえるといいですね。
日時:平成28年度11月20日(日曜日)
場所:野の鳥の丘公園
参加者:大人12名 子供2名 計14名
講師:木内 清氏(日本鳥学会会員)
依田 昌晃氏(東信自然史研究会)
カブトムシの飼い方講座を実施しました!
まずはカブトムシの特徴について勉強しました!
土の中からカブトムシの幼虫を掘り当てました。
カブトムシの生態について知る良い機会となりました。
まずは座学にて昆虫の種類や生態、カブトムシの特徴、どのような一生を送るのかについて勉強しました。
その後いよいよ、幼虫掘りへ。腐葉土の中から幼虫を見つけ出しました。カブトムシの幼虫は大きいのでみなさんすぐに見つけることができたようです。
一年後には立派なカブトムシになるといいですね!!
日時:平成28年10月15日(土曜日)
場所:昆虫体験学習館
参加者:大人21名 子供26名 計46名
講師:金子 順一郎氏(昆虫体験学習館館長)
秋の植物観察会を実施しました!
春の植物観察会にひきつづき、秋の植物観察会を開催しました!講師は春と同じく、自然観察インストラクターの中山 冽先生、場所は平尾山公園にて、秋の自然を堪能しました。
夏を終え、植物たちはすでに冬支度を始めているようで、珍しい草花がないのではと心配しましたが、今回は、よく目にする身近な雑草や草木の名前の由来や生態、特徴をお聞きすることができました。雑草にもたくさんの豆知識があり、参加者のみなさんはメモをとったり、質問をするなど、充実した秋のひと時を過ごすことができました。
日時:平成28年9月7日(水曜日)
場所:平尾山公園
参加者:大人16名
講師:中山 冽 氏 (自然観察インストラクター)
昆虫観察会を実施しました!
7月に開催した昆虫観察会では、昆虫体験学習館の金子館長さんに講師をしていただき、平尾山公園内を探検しました。日差しが強く暑い日でしたが、子どもたちは自由に走り回り、オオムラサキ、エドゼミ、バッタなどをみつけることができました。
また、昆虫だけではなく、平尾山に生息するきのこや、草花、木のお話しも聞くことができ、佐久の自然について学ぶよい機会となりました。
日時:平成28年7月10日(日曜日)
場所:平尾山公園内
参加者:大人8名 子供11名
講師:金子 順一郎氏 (昆虫体験学習館 館長)
春の植物観察会を実施しました!
春の植物観察会は、6月の梅雨真っ只中の開催でしたが、お天気にも恵まれ、大勢の皆様にご参加いただくことができました。美笹自然観察園は湿地性豊かで様々な植物が観察できるスポットなのですが、今回は、ハクウンボク、ウバユリ、ヤマアジサイなどの珍しい植物を観察することができました。
また、自然インストラクターの中山 冽先生に解説いただき、植物の名前や由来、豆知識などをお聞きすることができ、大変おもしろかったと好評をいただきました。
日時:平成28年6月19日(日曜日)
場所:美笹自然観察園
参加者:大人25名 子供1名
講師:中山 冽氏 (自然観察インストラクター)
平成27年度自然観察会の様子
野鳥観察会を実施しました
当日は、先生の解説を交えながら、双眼鏡や望遠鏡を使ってバードウォッチングを楽しみました。
マガモやカワウ、モンクロハジロにカイツブリなどさまざまな野鳥を観察することができ、寒いなかではありましたが、貴重な体験となりました。
日時 平成27年12月6日 日曜日 午前10時から正午まで
場所 野の鳥の丘公園(佐久市中込杉ノ木貯水池)
参加者 大人8名
講師 木内 清氏、小柳 恭二氏、依田 昌晃氏
カブトムシ飼い方講座を実施しました
当日は、先生よりカブトムシの飼い方や幼虫の生態についてご講義いただいた後に、幼虫掘りを行いました。
子供たちからカブトムシの飼い方や生態について質問が出たり、館内を見学したときは、普段なかなか目にしない昆虫の展示物に大人の皆さんも見入っていました。
日時 平成27年10月4日 日曜日 午前10時から正午まで
場所 平尾山公園
参加者 大人21名 子供29名
講師 井出 勝久氏
川の生きもの観察会(千曲川)を実施しました
当日は、ミズカマキリやヌマエビ等のほかに、めずらしいシマドジョウやアメリカザリガニ等も採集できました。
捕まえた生きものから水質判定を行い、調査地点の水はきたない水という結果でした。
日時 平成27年8月9日 日曜日 午前10時から正午まで
場所 鳴瀬 千曲川
参加者 大人9名 子供11名
講師 篠澤 明剛氏
川の生きもの観察会(湯川)を実施しました
当日は、タイコウチやウグイ、ヌマエビなどの川の生きものの他に、オハグロトンボといった珍しい昆虫も観ることができました。
捕まえた生きものから水質判定を行い、調査地点の水はややきれいな水という結果でした。
日時 平成27年7月26日 日曜日 午前10時から正午まで
場所 岩村田 湯川
参加者 大人5名 子供8名
講師 篠澤 明剛氏
昆虫観察会を実施しました
当日は、先生よりカブトムシやクワガタの生態についてやセラピーロード「ファーブルの小径」にてシロスジカマキリの生態や特徴を通して、現在の自然環境について説明をいただきました。
子供たちは、先生のお話を熱心に聞いていました。また、公園内でカブトムシを捕まえた子もいました。
日時 平成27年7月12日 日曜日 午前10時から正午まで
場所 平尾山公園
参加者 大人14名 子供20名
講師 井出 勝久氏
平成26年度自然観察会の様子
野鳥観察会を実施しました
日時 平成26年12月7日 日曜日 午前10時から正午まで
場所 野の鳥の丘公園(杉の木調整池)
参加者 大人10名 子供3名
講師 木内清氏、辻明子氏、依田昌晃氏
同じ種類の鳥でもオスとメスで見た目が違うの?潜るカモと潜らないカモの違いって?普段はなかなか気にかけることのない野鳥ですが、目を向けてみるとさまざまな発見がります。
当日は、専門の先生に野鳥の特徴や生態などの説明を聞きながら、バードウォッチングを楽しみました。
感想
「生まれて初めて双眼鏡を使って、ちょっぴりピントを合わせるのに手間取ったけど楽しかったです。もっと野鳥を見てみたいです。
「寒かったですが、有意義な時間でした。」
「たくさん鳥が見れて楽しかった。」
子供たちに見つけた鳥や周りの自然についてチェックしてもらうビンゴカードを配布しました。
昆虫観察会を実施しました
日時 平成26年9月27日 日曜日 午前10時から正午まで
場所 平尾山公園(雨天のため昆虫体験学習館で実施)
参加者 大人12名 子供18名
講師 井出勝久氏
当初、平尾山公園内にて昆虫採集、カブトムシの幼虫掘り体験を実施する予定でしたが、台風のため昆虫体験学習館での学習会となりました。
スクリーンや標本で昆虫について学んだあとは、いよいよカブトムシの幼虫掘り。子供たちはプラスチックケースに入った土に埋まっている幼虫を手で一生懸命掘り出していました。
感想
「身近な生物で知らないことがたくさんあり、興味深いたのしい話が聞けました。佐久の四季、環境の良さを実感しました。」
「昆虫のことを学ぶことが出来て良かったです。今後外で見つけた時に今までとは違う見方ができそうです。」
「よう虫がさわれたり、ヘラクレスオオカブトをはじめてみてとても楽しかった。きちょうな体験ができた。」
「もらったよう虫を大切に育てます。」
「こうした体験を通して子供たちに環境問題にも目を向けていってほしいし、私自身も向けたいと思います。」
川の生きもの観察会を実施しました
日時 平成26年7月27日 日曜日 午前10時から正午まで
場所 千曲川(千曲川スポーツ交流広場付近)
参加者 大人16名 子供19名
講師 篠澤明剛氏
ミズカマキリやトビゲラ類、ナミウズムシ等のほかに、めずらしいシマドジョウ等も採集できました。この観察会で川には魚だけでなくいろいろな生き物がすんでいることを実感していただけたのではないでしょうか。
また、採集した水生生物をもとに水質の判定をし、水質によってすむ生き物が異なるということを学習しました。
詳しくは以下資料をご覧ください。
採集した生き物の集計と講師の先生による考察をまとめました。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ