更新日:2026年1月1日
1月は、内田あぐり《三態》を紹介します。
「月替わりコレクション紹介」について
《三態》
制作者 内田あぐり
制作年 1982年
材質・技法 紙本彩色
寸法 180.0×270.0センチメートル
《三態》には、立姿の三人の裸婦像が描かれています。制作者である内田も、鑑賞者である我々も《智・感・情》を意識せずにはいられないでしょう。
明治から大正期にかけて活躍した洋画家・黒田清輝(1866-1924)が寓意的な表現を試みた作品として有名な《智・感・情》(1897年制作※)は、三枚の画面で構成された絵画で、金地を背景にそれぞれ智、感、情を意味すると思われるポーズをとった裸の女性像が一画面に一体ずつ描かれています。黒田は、当時、風紀上の観点からのみで裸体画を問題視する日本の社会に抗議する意味もあって、理想化した裸婦像を描いたと思われます。
《三態》の裸婦像は、形をみれば理想形ではなく、色についていえば肌の色とは似ていない白と黒で描かれているのですが、体の形や筋肉のつながり、その弾力などを、生々しく感じることができます。「態」という字には形、姿、ふるまいなどの意味もあるようです。内田は1982年、実在していた女性をモデルにしてドローイングを何枚も描いたのち、本作を制作したのでしょう。この女性の像三体の、姿やふるまいから、当時の街の空気感や社会の状況までも感じられるようです。
本作は初期の作品ですが、内田はその後も人体を一つのテーマとして取り組み、人体のドローイングやエスキス作品の制作、展示も行ってきました。
内田あぐり(1949-)
東京に生まれる。武蔵野美術大学で日本画を学ぶ。在学中の1972年第35回新制作展に初入選、その後創画会に参加。大学院修了年に創画会賞を受賞するなど早くからその実力が評価されており、ほかにも数々の受賞歴がある。1993年文化庁在外研修生として渡仏、2003年から武蔵野美術大学在外研究員として渡米。武蔵野美術大学や金沢美術工芸大学で教鞭を執るなど後進の指導にもあたる。
註
※《智・感・情》の制作年について、黒田記念館のウェブサイトに次のように記載されている。「明治30(1897)年、第2回白馬会展に『智・感・情』の題で出品した三部作。のち、三画面とも加筆され明治33年パリ万博に『裸婦習作』として出品され銀賞を受けた。」(https://www.tobunken.go.jp/kuroda/gallery/japanese/tikanjo01.html・2026年1月7日閲覧)
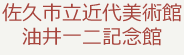
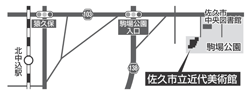
毎週月曜日(休日の場合は開館)
展示替え期間(不定期)
年末年始期間(12月29日~1月3日)
ほか臨時休館することがあります。
午前9時30分~午後5時