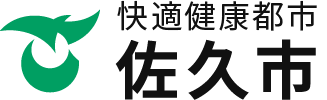【ノロウイルス食中毒注意報が発表されました】冬季に流行する感染症に注意しましょう
更新日:2026年1月14日
県内に「ノロウイルス食中毒注意報」が発表されました。(令和8年1月14日)
長野県内において、感染性胃腸炎患者の届出数に増加傾向が見られることから、県内に「ノロウイルス食中毒注意報」が発出されました。
手洗いを徹底し、食品の取扱いには十分注意して、食中毒を予防しましょう。![]() 「ノロウイルス食中毒注意報」を全県に発出しました。/長野県(外部サイト)
「ノロウイルス食中毒注意報」を全県に発出しました。/長野県(外部サイト)
県内に「インフルエンザ警報」が発表されました。(令和7年11月19日)
長野県感染症情報(11月10日~11月16日)で、インフルエンザの定点当たりの患者数が30.61人となり、警報の基準値である30.00人を上回ったことから、インフルエンザ警報が発表されました。
しばらくの間は流行の継続が予想されますので、「かからない」「うつらない」ように十分注意し、感染予防・拡大防止を心がけましょう。![]() 【訂正版】インフルエンザ警報を発表します/長野県(外部サイト)
【訂正版】インフルエンザ警報を発表します/長野県(外部サイト)![]() インフルエンザ情報(季節性インフルエンザ)/長野県(外部サイト)
インフルエンザ情報(季節性インフルエンザ)/長野県(外部サイト)
県内に「インフルエンザ注意報」が発表されました。(令和7年11月12日)
長野県感染症情報(11月3日~11月9日)で、インフルエンザの定点当たりの患者数が11.51人となり、注意報の基準値である10.00人を上回ったことから、インフルエンザ注意報が発表されました。![]() インフルエンザ注意報を発表します/長野県(外部サイト)
インフルエンザ注意報を発表します/長野県(外部サイト)
空気が乾燥し、気温が低くなる冬は様々な感染症が流行します
冬の季節は例年インフルエンザをはじめ、RSウイルス感染症、ノロウイルス食中毒といった感染症が流行します。
季節性インフルエンザ
一般的な風邪は様々なウイルスによって起こりますが、その多くは、のどの痛み、鼻汁、くしゃみや咳などの症状が中心で、全身症状はあまり見られません。発熱もインフルエンザほど高くなく、重症化することはあまりありません。
一方、インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。飛沫や接触により感染し、38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など全身の症状が突然現れます。併せて一般的な風邪と同じように、のどの痛み、鼻汁、咳などの症状も見られます。小児ではまれに急性脳症を発症し、高齢の方や免疫力の低下している方では肺炎を伴うなど、重症になることがあります。
予防法
- 感染経路を断つ
帰宅時や調理の前後、食事前など、こまめな手洗いを心掛けましょう。アルコールを含んだ消毒液で手を消毒するのも効果的です。
- 流行前にインフルエンザの予防接種を受ける
発症する可能性を減らし、もし発症しても重い症状になるのを防ぎます。
- 免疫力を高める
ふだんから十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ、免疫力を高めておきましょう。
RSウイルス感染症
RSウイルスは飛沫や接触により感染します。感染すると発熱、鼻汁などの症状が数日続きます。急性脳症、肺炎等の重篤な症状を引き起こすことがあるため、感染によって重症化するリスクの高い基礎疾患を有する小児(特に早産児や生後24か月以下で心臓や肺に基礎疾患がある小児、神経・筋疾患やあるいは免疫不全の基礎疾患を有する小児等)や、生後3か月以内の乳児への感染には特に注意が必要です。
予防法
- 感染経路を断つ
帰宅時や調理の前後、食事前など、こまめな手洗いを心掛けましょう。アルコールを含んだ消毒液で手を消毒するのも効果的です。
お子さんが日常的に触れるおもちゃ、手すりなどはアルコールや塩素系の消毒剤などでふき取り消毒をしましょう。
ノロウイルス食中毒
感染から発症までの時間(潜伏期間)は24時間~48時間で、主に手指や食品などを介して感染し、主な症状は吐き気、おう吐、下痢、腹痛、37℃~38℃の発熱などです。通常、これらの症状が1~2日続いた後、治癒します。また、感染しても発症しない人や、軽い風邪のような症状で済む人もいます。ノロウイルスは感染力が強く、食中毒など集団感染を引き起こしやすく、持病のある人や乳幼児、高齢者などは、脱水症状を起こしたりと重症化するケースもあるので注意が必要です。
予防法
ノロウイルス食中毒の予防4原則
(1)ノロウイルスを「持ち込まない」
調理する人がノロウイルスに感染していると、その人が調理した食品を食べることによって多くの人にノロウイルスが二次感染してしまいます。ノロウイルスによる食中毒を防ぐためには、調理場にウイルスを持ち込まないことが重要です。家庭で調理する方や、食品をつくる仕事をしている方は、次のようなことを心がけましょう。
- ふだんから感染しないように、丁寧な手洗いや日々の健康管理を心がける。
- 腹痛や下痢などの症状があるときは、食品を直接取り扱う作業をしない。
(2)ノロウイルスを「つけない」
食品や食器、調理器具などにノロウイルスを付けないように、調理などの作業をする前などの「手洗い」をしっかりと行いましょう。
手を洗うタイミング
- トイレに行った後
- 調理施設に入る前
- 料理の盛り付けの前
- 次の調理作業に入る前
- 手袋を着用する前など
(3)ノロウイルスを「やっつける」
食品に付着したノロウイルスを死滅させるためには、中心温度85℃~90℃、90秒以上の加熱が必要です。
調理器具は、洗剤などで十分に洗浄した後に、熱湯(85℃以上)で1分以上加熱するか、塩素消毒液※(塩素濃度200ppm)に浸して消毒します。
(4)ノロウイルスを「拡げない」
ノロウイルスが身近で発生したときには、ノロウイルスの感染を広げないために食器や環境などの消毒を徹底すること、また、おう吐物などの処理の際に二次感染しないように対策をすることが重要です。
担当係:保健予防係
お問い合わせ
電話:0267-62-3196(健診推進係)、0267-62-3527(保健予防係)、0267-62-3189(健康増進係)、0267-63-3781(口腔歯科保健係) 、0267-62-3524(保健医療政策係)
ファックス:0267-64-1157