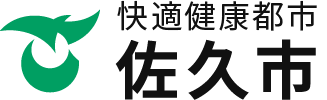台風接近に伴う農作物等の技術対策について
更新日:2025年9月4日
台風接近に伴う農作物等の技術対策について
台風が接近し大雨や強風が予想される場合は、農業者の方は対策として、以下の点について対応をお願いします。
1 共通
(1)気象情報に十分留意するとともに、ほ場の排水が速やかに行われるよう、滞水しやすいほ場を中心に周辺の整備や排水路の点検を行う。ただし、風雨が強く、河川や水路が増水して危険が予想される場合は、危険箇所に近づかない。
(2)冠水しやすい場所では、事前に機械類等を移動しておく。
(3)突風に備えて、果樹や野菜・花き類の支柱、施設・温室の外周りなどを点検・補強する。特に、傷んでいる箇所や力が大きくかかる箇所に注意する。また、作業は複数人で行う。
(4)台風通過後の対策で農薬散布を行う際には、最新の農薬使用基準を遵守する。
(5)農作業機械の移動にあたっては、事前に通行路の安全性を確認するなど、事故防止に努める。
2 園芸・農業用施設全般
(1)強風に備えて、ハウスや畜舎及び堆肥施設等の破損部の修理、支柱・筋交い等の補強を行う。特にパイプハウスは強風による被害を受けやすいので、ハウスやフィルムが飛ばされないよう、らせん杭の設置やフィルム押さえバンド、フィルム留め具等の点検を行っておく。
施設の周囲に排水溝を設け冠水を防ぐ。
(2)サイドフィルムのあるパイプハウスでは、サイドフィルムを下ろし、妻部分もフィルムで覆い、すきま風が入らないようにする。ただし日中気温の高い状態では、風下妻面のみを開放し、台風通過後、速やかにハウス内を換気する。
(3)雨よけ施設では、状況に応じてフィルムの巻き上げを行い、施設の損壊を防ぐ。
(4)収穫終了後など使用していないハウスは、被覆資材(フィルムやネット等)を取り外す。
(5)倒壊が心配される場合の最終手段として被覆フィルムを切り裂き、風圧を軽減する手段を検討する。ただし、強風の中の作業は大変危険であるため安全確保を最優先する。
(6)防鳥ネット、防雹ネット、日焼け防止ネット(寒冷紗等)設置園では、強風で飛ばされないようネットの巻き取りや除去を行う。
3 水稲
(1)事前に排水路の詰まり等の点検・補修を行い、冠水時の速やかな排水に備える。 冠水した場合は速やかに排水する。
(2)成熟期前のほ場で、台風通過後にフェーン現象による高温乾燥が発生した場合は十分な灌水を行う。
(3)台風によって倒伏した水田は風が収まるのを待って早急に排水し乾燥を促す。出穂後30日以上を過ぎているものは速やかに収穫の手配を行う。
(4)はざ干しは倒れないよう補強すると共に、倒れた場合は早急に立て直し、乾燥を促して穂発芽の発生を防ぐ。
4 大豆・そば
浸水・冠水した場合は、直ちに排水する。また、大豆では病害虫の発生に注意し、適切に防除を行う。
5 果樹全般
(1)収穫直前の果実については、JAや集出荷業者等と十分協議のうえ、収穫可能な品質に達している果実を収穫する。なお、収穫に当たっては農薬使用基準(収穫前日数)を遵守するとともに、未熟果を収穫しないようにする。
(2)高接ぎを行った樹では、強風で接木部や新梢が折損しないよう、立木果樹では添え竹に結束し、棚果樹では亜主枝候補など重要な場所はできるだけ誘引ひもで振れ止めの処理を行う。
(3)滞水しやすいほ場では、園の周囲に排水溝を設置して早期排水に努める。また浸水・冠水した場合は、直ちに排水する。
6 立木果樹(りんご、もも、プラム、プルーン、おうとう等)
(1)樹の倒伏・折損を防ぐために、防風ネットの展張と点検、支柱の追加、主枝の固定等を行う。日焼けが発生した骨格枝や腐らん病、虫害被害部は折れやすいので、しっかり固定する。
(2)3~6年生程度の若木は倒伏しやすいので、主幹部に必ず支柱を添え、トレリスの固定を確認する。特に苗木は倒伏しやすいので、支柱にしっかり固定する。
(3)トレリスのアンカーや架線の緩みを点検し、必要に応じて締め付けを行う。また、振れ止め線を中柱に固定する。
(4)日焼けを軽減するため被覆資材を設置している場合は強風による樹体・果実の被害が発生する。これらの被害を回避するため、被覆資材を取り除く。
7 棚果樹(なし、ぶどう等)
(1)棚の周囲に防風ネット等を張り、風による果実の落果や枝の損傷を防ぐ。
(2)棚の上下動に伴う枝の損傷や落果を防ぐために、アンカーの補強、棚線の締め直し、ゆるんだ誘引部の補強等を行う。特にAマストの棚は、強風により棚全体が上下動しやすいため、アンカーと引き張り線による補強を徹底する。
(3)ぶどうでは、こまめに新梢誘引を行い、房が風で振られないようにする。
8 野菜、花き(露地栽培)
(1)露地のきゅうり、アスパラガス、ながいも、スイートコーン、花き類(きく、りんどう、ゆり、グラジオラス等)などは支柱の補強やフラワーネット等の補修を行い、強風による倒伏と茎葉等の損傷を防ぐ。
(2)滞水しやすいほ場では、畑の周囲へ排水溝を設置して早期排水に努める。
(3)台風通過後、滞水が続いた場合は、液肥の葉面散布を行い草勢の回復を図る。
(4)強風や雨により病害が発生、拡大する恐れがあるので、台風通過後、風が収まるのを待って、速やかに殺菌剤の散布を行う。台風通過後薬剤散布が難しいほ場では、特に殺菌剤の予防散布を徹底する。
(5)スイートコーンは、雌穂絹糸抽出期前で倒伏した場合、不受精による変形果の発生が懸念されるので、根を傷めないよう早めに起こす。
(6)きく、りんどう、ゆり、グラジオラス等が倒伏した場合は、早めに茎葉を起こし、茎の曲がりを防ぐ。
9 畜産
(1)畜舎周辺を点検し、雨水の流入、浸水等がないように周囲の排水対策を行う。
(2)餌タンクや資材庫についても同様に点検し、雨水の流入、浸水等がないように周囲の排水及び雨漏り対策を行う。
(3)ハウス畜舎、堆肥舎は破損部の補修、支柱・筋交い等の補強により倒壊を防ぐ。特に強風によりフィルムが飛ばされないようフィルム押さえバンドを点検する。
(4)停電に備え、搾乳機やバルククーラーの電源を確保するための自家発電機の点検を行う。発電機の準備が無い場合はJA等、関係団体と連携を取り災害発生時の対応について協議する。
10 菌茸
(1)空ビン、キャップ等の風で飛ばされやすい資材は倉庫など安全な場所に移動させ、オガコは飛散防止のためにシートなどで覆う。
(2)施設の出入り口で雨水の流入する可能性がある場所には事前に土のうや止水板などを設置して、流入防止対策を行う。
(3)停電が発生し室温と外気温の差が大きい場合は、短時間であればドアの開閉を控える。
(4)停電が長時間にわたる場合は、施設内の温度上昇に留意して適宜、換気を行う。
(5)施設が浸水した場合は、次の対策を行う。
・電気設備は、起動前に十分な点検を行い、漏電事故が発生しないよう注意する。
・収穫できるものは、早めに収穫、包装する。
・生育中、水がかかった生産物は速やかに施設外へ搬出し、処分する。
・室内の浄化を図るため、施設を空にして水で泥等を洗浄する。
・洗浄後は、除菌剤(0.1~0.05%次亜塩素酸ナトリウム)を散布し、乾燥させる。
オゾンガス発生装置がある場合は、オゾン処理方法に従って除菌する。
・次亜塩素酸ナトリウム散布後は、十分換気してから培養基を搬入する(直後の搬入は避ける)。
11 鳥獣害対策
(1)広域防護柵、簡易電気柵を点検し、支柱の補強・通電線の張りの調整を行う。
(2)台風通過後、倒木等による破損や漏電が確認された場合は、速やかに修繕する。