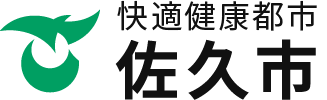水産物
更新日:2022年4月21日
 佐久鯉
佐久鯉
 シナノユキマス
シナノユキマス
 信州サーモン
信州サーモン
 鮎
鮎
| 佐久鯉 | 全国ブランドとして名高い「佐久鯉」は、発祥から220年以上の長い歴史があります。 昭和初期には、全国一の生産量とともに、鯉の品評会等でもその優れた品質で日本一の称号を得ました。そして、当時の宮内省や陸軍の御用達の栄を賜り、その名声をますます天下に轟かせました。 「佐久鯉」は、1年目を当歳(とうざい)、2年目を中羽(ちゅうっぱ)、3年目の鯉を切鯉(きりごい)と呼び、3~4年で出荷となります。 温暖な他県産地の鯉は、2年ほどで出荷されるところ、「佐久鯉」は佐久の気候や風土と、千曲川の清冽な冷水で飼育されるため成長が遅く、飼育期間がかかりますが、それだけに臭みがなく、身の締まった美味しい鯉が生産されています。 代表的な「佐久鯉」料理として、あらい・鯉こく・うま煮(甘露煮)・塩焼きなどの伝統食のほか、新巻鯉・味噌漬け・鯉丼・うろこ揚げなどの料理が、地元はもとより、県外からの観光客等にも愛されています。 また、平成20年9月に、特許庁より地域団体商標として認定されたことを契機に、「佐久鯉」養殖の中心を担う佐久養殖漁業協同組合と、市内の加工・販売・流通業者等が連携し、地域ブランドの高揚に向けた取り組みが行われいます。 |
|---|---|
| シナノユキマス | 『シナノユキマス』は、サケの仲間で、サケ科コレゴヌス属に分類される外国から来た冷水性の魚です。 長野県には、1975年に旧チェコスロバキアから卵が導入されて以来、長期にわたる長野県水産試験場佐久支場の試験研究の結果、養殖技術の確立に成功し、本格的な生産が始まりました。 名前の由来は、「雪を連想させる銀白色の姿」から、当時の長野県知事により、『シナノユキマス』と名付けられました。 シナノユキマスの肉質は、白身の淡泊な味が特徴で、適度な脂がのり、小骨が少ないことから、和食・洋食・中華のいずれの料理にも合います。 事業規模で生産されているのは主として長野県だけであり、その中でも佐久市における生産は県全体の約8割を占め、主産地となっています。 |
| 信州サーモン | 『信州サーモン』は、バイテク技術によりニジマスとブラウントラウトを交配させて作り出した新しい魚です。 ニジマスに比べて成長が早く、肉質のきめが細かく肉厚であるとともに、卵や精子を持たず成熟しないことから肉質が一定し、また、病気に強いなど優れた特徴を持っています。 県内外のレストラン等でも、淡水魚特有の臭みがない、舌ざわりがよい、脂ののりが適度であるなどの評価を得て、洋風・和風を問わず広く使われています。 長野県は活魚として県外に出すことを禁止するとともに、卵も長野県水産試験場でしか生産・供給できないことから県内のみの養殖に限られており、佐久市では全体の2~3割程度を生産しています。 |
| 鮎 | 千曲川では、6月第4土曜日か7月第1土曜日が鮎の解禁日となっています。 香魚とも呼ばれ格別な味わいがある鮎は、縄張りつくる習性があることから、「友釣り」と呼ばれる釣り方をします。 ※友釣りの情報は、佐久漁業協同組合(電話:0267-62-0764)へ。 |
佐久鯉の情報
佐久鯉を提供している店舗の情報はガイドブックをご覧ください。
(令和3年12月末時点の情報です。提供には事前予約が必要な場合がありますので、各店舗にご確認をお願いします。)![]() 佐久鯉ガイドブック(PDF:2,544KB)
佐久鯉ガイドブック(PDF:2,544KB)
佐久鯉の新しい食べ方
佐久鯉を美味しく食べましょう。
外部サイト![]() 信州佐久・佐久鯉ガイド(外部サイト)
信州佐久・佐久鯉ガイド(外部サイト)![]() 佐久市観光協会(外部サイト)
佐久市観光協会(外部サイト)
佐久鯉の魅力発信 PR動画![]() 佐久鯉 ~佐久の風土と人が育む名産品~(外部サイト)
佐久鯉 ~佐久の風土と人が育む名産品~(外部サイト)![]() 佐久鯉の食文化継承(外部サイト)
佐久鯉の食文化継承(外部サイト)![]() 魅力満載佐久地域のフード 佐久鯉(外部サイト)
魅力満載佐久地域のフード 佐久鯉(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ