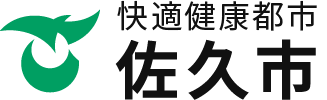令和7年度 佐久市ふるさと創生人材育成事業 中学生海外研修(モンゴル国)報告
更新日:2025年9月11日
令和7年度 中学生海外研修(モンゴル国)報告 引率団長 武者新一
1 研修の概要
(1)目的
次世代を担う青少年の人材育成事業の一環として、モンゴル国の一般家庭や遊牧民宅のゲルでのホームステイ、子ども交流会を通して相互理解を深め、モンゴル国の風土や文化を肌で感じることで国際的視野を広げることを目的とする。
なお、本事業は、平成22年から実施しているが、途中新型コロナウイルス禍等による中断があったため、今回は通算で12回目開催であった
(2)日程
令和7年7月27日(日曜日)から8月3日(日曜日)までの8日間
(3)研修地
モンゴル国
・アラブルドツーリストキャンプ場 周辺遊牧民宅(ゲル) 2泊
アラブルドツーリストキャンプ場 1泊
(チンギスハーン騎馬像、ゲル作り体験、乗馬体験、ラクダ乗馬体験)
・ウランバートル市スフバートル区
(ホストファミリー宅3泊、フラワーホテル1泊、スフバートル広場、ノミンデパート、在モンゴル日本大使館、スフバートル区役所、日本人墓地公園、チンギスハーン博物館見学、モンゴル民族歌舞鑑賞(馬頭琴の演奏)
(4)参加者
研修生:市内中学生8名(1年生2名、2年生4名、3年生2名)
引率者:2名(佐久市職員)
添乗員:2名(株式会社日本旅行佐久平サービス)
2 事前研修
令和7年6月5日~7月19日までの間、週1回のペースで合計8回に渡って、事前研修を行った。事前研修では、研修日程や研修期間中の留意事項等について説明を伺ったほか、研修生一人ひとりの役割分担を決めたのち、現地での子ども交流会で披露する佐久市の紹介及び出し物(歌、ゲーム)並びに生徒たちがモンゴルで行う研究課題について、内容決定のための話し合いやその練習に専ら取り組んだ。
引率者としては、自らも研修チームの一員であることを自覚し、信頼関係が築けるよう、また、単なる同行者とならないよう、積極的に子どもたちに関わることを心掛け、毎回の冒頭の挨拶の中で士気を高め、天皇陛下もモンゴル国を訪問されたことを紹介するなどしてモンゴル国に関心を持たせるよう工夫し、さらに、話し合いや歌の練習にも積極的に参加した。
事前研修では、事務局より毎回のように宿題が出され、終了予定時刻の9時を過ぎることも度々あった。研修生にとって少なからず負担になっていたと思うが、回を重ねるごとにお互いの気持ちが通じ合い、チームワークの醸成や期待感の高まりが手応えとして感じられ、事前研修を行うことができた。
7月19日に行われた壮行会では、市長、教育長はじめ、教育委員、ふるさと創生人材育成事業実行会の委員らをお招きするとともに研修生の保護者の方々にも出席いただき、エストニア共和国への研修生とともに、グループ研修課題の発表に続き、研修先で披露する歌の斉唱を行った。この壮行会を通してそれぞれが、いざモンゴルへという気持ちが一層高まったと感じた。6月の1回目の研修会では、8回もの研修会は非常に長いと感じたが、あっという間の2か月間であった。
3 第1日目 7月27日(日曜日)
佐久平駅にて、中澤実行委員長、春原氏(佐久市・モンゴル親善協会 会長)、社会教育部長、生涯学習課職員、研修生の保護者、歴代の引率者の方々の出席のもと出発式を行っていただいた。2ヶ月前より事前研修を行ってきたが、今になってはあっという間の2ヶ月だった。大勢の方の見送りを受け、「いざ、モンゴルへ」。
その後、新幹線あさま号の中では、みんなでトランプ遊びをし、あっという間に上野駅へ到着。徒歩にて移動し、京成スカイライナーを経由し、成田空港へ到着。予め、送ってあったスーツケースを受け取り、スーツケースを搭乗機へ預け入れ、空港内で昼食を取った。重いスーツケースを持ち運びしなくて済んで非常に楽であった。昼食後、いよいよ出国。手荷物検査、保安検査、出国審査などの諸手続きを慌ただしく済ませ、ミアットモンゴル航空へ搭乗した。搭乗機は、1時間程遅れてのフライトとなった。飛行時間は、約5時間、無事チンギスハーン国際空港へ到着。入国審査は、パスポート及び航空券提示し、ジロジロと見られハラハラドキドキしたが、無事審査終了。現地時間、午後8時であったが、外はまだ凄く明るかった。空港をバックに皆で記念撮影。
空港では、現地スタッフのテムジン氏(男性)、ボロル氏(女性)、スフバートル区役所職員ボヤ氏の出迎えを受け、マイクロバスにて空港より1時間ほど離れたウランバートル市内のフラワーホテルへ向かう。空港から、ホテルまで雄大な草原の景色を眺めながら、どこまでもまっすぐな高速道路に感動した。車中でサンドイッチとペットボトルの水をもらったが、機内食を食べたせいか、お腹がいっぱいのため食べることができなかった。車窓より、スフバートル市内を眺めたが、大きなビルが立ち並び大都会だと感じた。また、テムジン氏より、市内を走っている車は、日本車が多いとの説明を受けた。中でもトヨタ車が圧倒的に多かった。
慌ただしく、ホテルへ到着すると既にホストファミリーが待っており、温かい出迎えを受けた。子どもたちは、各々緊張した面持ちで対面式を行った。終了後、息をつく間もなくそれぞれ家庭へホストファミリーの車で移動。初めて訪れるモンゴルとホストファミリー宅への宿泊にきっと緊張したことだろう。
第2日目 7月28日(月曜日)
午前4時に起床し、アラブルドツーリストキャンプ場と遊牧民宅で過ごすため、3日分の着替えをリュックサックに詰め込んだ。
子どもたちは、午前8時にフラワーホテル集合。スフバートル区の研修生8名も一緒にバスに乗り込み、バスとワゴン車の2台でアラブルドツーリストキャンプ場へ移動。事前に道路状況は、3分の1は良い舗装、3分の1は、程度の落ちる舗装、残り3分の1は、未舗装と聞いていたので、酔い止めの必要な子どもへは、酔い止めを配布した。説明どおり、前半は快適な道路であったが、徐々に揺れを感じ始めた。後半は、道なき道を進み激しい揺れを体感、幸いにもバス酔いする者はいなかった。3時間ほどかけキャンプ場到着。到着後、ゲルにて皆で昼食を取った。
昼食後、4家族の遊牧民宅へ子どもたちを送り届けた。未知の体験に夢膨らませる子や不安気な子どもの姿が見受けられた。子どもたちを送り届けた際、各家庭で作った、チーズ、馬乳酒をいただいた。馬乳酒は、カルピスの原点であると聞いていたが、ちょっと酸味の効いた飲み物だった。どんぶりのような大きな器で提供されたが、慣れていない人はお腹を壊すと聞いていたので全部飲み干すことは出来なかった。チーズは、固めで普段食べているものと違った味であった。遊牧民宅には、バイク、車が各家庭にあった。家畜を集める際、バイク、車を使うと聞いて、想像と違うことにちょっとしたカルチャーショックを受けた。ゲルには、太陽光発電設備、Wi-Fi、テレビが備え付けられていた。
研修生たちと別れ、現地スタッフ及びスフバートル区役所の担当職員3名の一行は、ツーリストキャンプ場にて宿泊。夕食後に見た、地平線へ沈む夕日と三日月のコントラストがすばらしかった。海で地球の丸さを感じるというが、モンゴルでは草原でそれを感じた。12時以降は、現地スタッフ曰く、百万年に一度と言われる二大流星群を見ることができるとのこと。障害物、明かりが一切ないので星空がとてもキレイだった。手に届きそうな星空だと感じた。子どもたちもきっと遊牧民のゲルで見ていることだろうと考えながら流れ星を観察した。30分ほどの間に5つの流れ星を見ることができた。
第3日目 7月29日(火曜日)
明け方、目を覚ますと、暗闇の中、馬の鳴き声が響き渡っていた。
キャンプ場は、想像していたよりキレイで、温水シャワー、水洗式トイレ(ウォシュレット式)が完備していた。
今日も、快晴。無風、ゲルのご主人にコーヒーをいただいた。ご主人は、かつて日本に居たことがあり、日本語も少し話せた。ゲル内は、ストーブで暖を取っていた。思っていたほど、外気温は低くなく過ごしやすい環境だった。
午前10時に、子どもたちの様子を見にゲルを訪問した。子どもたちは、パン作り、バイクへの乗車、シューマイ作り、馬乳酒作り、乳しぼり等それぞれの家庭で体験していた。若干ホームシックになり気味の子も見受けられたが、皆元気に過ごしていた。疲れのせいか、昨夜の星空を観察した子どもはいなかった。
午前中に3組の遊牧民宅を訪問。午後、残り1組の遊牧民宅を訪問した。
終了後、現地のスーパーマーケットと名の付くお店に寄った。都市部と違い、田舎は、未舗装の道路であった。お店も、日本で見かける個人商店のようなお店だった。

第4日目 7月30日(水曜日)
今日は、朝から雨。雨がゲルのテントをたたく音で目を覚ました。
佐久市では、毎日熱中症アラートが出ているようだが、モンゴルは清々しい気候。午前中、二手に分かれ子どもたちを遊牧民宅へ迎えに行った。片方の遊牧民宅までの道は、ワゴン車では行くことができず、ランドクルーザーで迎えにいった。遊牧民宅の子どもと仲良くなり、別れを惜しむ姿も見受けられ、その姿に、ちょっとウルっとした。
午後は、昼食後ゲル作り(20分)、解体体験(10分)、乗馬体験、そり遊び、ラクダ乗りを体験した。皆、初めての体験に目を輝かせていた。ラクダは、立ち上がる時は、後ろ足から立ち上がり、座る時は、前足をカックンと折りたたむので馬とは違いちょっとその衝撃に驚いた。乗り心地は、馬よりも大きく揺れると感じた。また、乗馬は、広い草原で行うため爽快感を感じた。一人当たり、引馬による15分ほどの時間であったが、もっと長く乗馬していたいと感じた。一方、モンゴルの研修生たちは、馬を上手に乗りこなしており遊牧民でなくとも乗馬ができることに驚いた。
夕食前に、子ども交流会を行った。まず、日本の子どもたちから発表を行った。事前研修の成果もあり、野外での発表であったが、大きな声で発表を行うことができた。ゲームは、「だるまさんが転んだ」を説明しながら行った。夕闇の中を懐中電灯の灯りを頼りに行ったが、モンゴルの研修生にも好評であったと感じた。ゲームを通してモンゴルの研修生との距離感がぐっと縮まったのではないか感じた。途中、夕食の時間になったため一端、中断。
夕食は、ヤギの尊い命を現地の調理法である石焼でいただいた。石焼とは、鍋に熱した石を投入する調理方法。
夕食後、キャンプファイヤーを囲みながら、交流会の続きを行った。交流会の最中に、はるか遠くで雷鳴が鳴り響き、空がオーロラのように光るのが幻想的であった。

第5日目 7月31日(木曜日)
9時30分にキャンプ場を後にし、スフバートル区へ移動。途中で、モンゴルの研修生、スフバートル区役所職員と別れ、日本の研修生だけでチンギスハーン騎馬像を見学した。高さ、40メートルという大きさに圧倒された。騎馬像のたてがみの所まで、エレベーターあるいは階段により登ることができた。そこには、世界一大きな長靴とムチも展示されていた。
その後、九州地方のチェーン店である「味千ラーメン」を食べた。久々の日本食に、一同、舌鼓を打った。やはり、食べ慣れた食事は美味しいと感じた瞬間だった。
昼食後、スフバートル広場から、国会議事堂の外観を見学。日本人が建築したと説明を受け、日本人の技術力の高さを痛感した。すぐそばには、TVドラマのVIVANTの舞台となったオペラ座を見学。もう一度、VIVANTを見てみようと感じた。その後、ノミンデパートを約1時間見学しお土産の品定めをする。みんな、真剣な眼差しでお土産の品定めを行っていた。デパートの見学後、ホテルへ帰った。
子どもたちは、モンゴルの研修生と再会しへホームステイ。

第6日目 8月1日(金曜日)
ホストファミリー宅からホテルへ集合し、8時30分にホテル出発。
スフバートル区役所を表敬訪問。区長と対談し記念撮影。個々にお土産までいただいた。大いに歓迎いただき感謝。その後、日本大使館を表敬訪問。大使館ではスマホ持ち込み禁止。厳重な警戒であった。大使は、大阪万博で不在であったが、森山賢美専門調査官、北澤彰浩参事官兼医務官(元佐久総合病院勤務)に対応をいただき。モンゴル国について、説明を受けた。日本とモンゴルの違いをスライドにより丁寧に説明いただいた。モンゴル国の男性の平均寿命65歳、女性74歳(日本:男性の平均寿命82.3歳、女性88.5歳)との説明を受け、日本人とかなりの差があることがわかった。原因は、食生活にあることがわかった。(モンゴル国は、肉中心の食生活)
次に、日本人墓地慰霊碑を訪問し、スフバートル区役所で用意いただいた菊を献花した。1,600人という多くの日本人が亡くなったことを知った。この場所は、つい先ごろ天皇陛下御夫妻が訪問し、献花を行った場所である。
昼食は、モンゴル料理の専門店でいただいた。昼食後、チンギスハーン博物館を見学。時間の都合上、9階に展示された黄金のチンギスハーン像のみ見学。
次に、馬頭琴の演奏までに、少し時間があったので、Eマート(コストコのようなお店)でお土産を購入した。研修生たちは、皆真剣に品定めをしながら、家族、友人等へのお土産を、現地通貨であるトゥグルク(1トゥグルク=¥0.045)を使用し購入。(本日、1万円を現地通貨へ換金しておいた。)あっという間の1時間でした。その後、徒歩にて馬頭琴の演奏会場へ移動。ビル一棟がそれぞれの劇場になっているような建物であった。馬頭琴の演奏会場(20人~30人程度入れる劇場)は、満員で椅子が足りず劇場スタッフが急遽追加の椅子を用意してくれ鑑賞した。
演奏鑑賞後、フラワーホテルへ戻り、各々ホストファミリー宅へ移動。

第7日目 8月2日(土曜日)
いよいよ、7日目。今日は終日フリータイム。研修生たちは、各々のホストファミリーとノミンデパートでの買い物、あるいは区内の遊園地等で過ごした。
引率者の日程も終日フリー。午前中は、お土産購入のためGobiカシミヤの専門店へ案内してもらい購入。
昼食は、ウズベキスタン料理の専門店にて食事。昼食後、岩塩等の購入のため地元スーパーへ。その際、思いがけず地元TV局の取材を受け佐藤副団長と通訳のテムジン氏で対応した。取材内容は、現地野菜の価格についてのようだった。)
次に、ノミンデパートへ移動し、買い足りていなっかった分の最後の購入をおこなった。スーツケースに収まるのかが心配・・・。
夕食は、ホテルのレストランにて日本大使館の北澤参事官兼医務官と会食。
20:00からは、最後の一日をホストファミリーと過ごした研修生を出迎えた。
第8日目最終日 8月3日(日曜日)
3:30にホテルにてモーニングコールをしていただき起床。
4:30集合、チェックアウトを済ませ、ホテルで用意いただいたサンドイッチと水をもらいバスに乗車し4:40ホテルを後にした。
バスにて、約1時間でチンギスハーン空港へ到着。慌ただしく、スーツケースを預けた。案の定、引率者の自分と副団長の佐藤さんは、スーツケースの重さ(23キロ)をオーバーのため追加料金が発生。スーツケースを預けた後、現地スタッフにお礼のあいさつを済ませ出国手続きを行った。保安検査場では、履いている靴も脱ぐよう言われちょっとびっくりした。モンゴルでの滞在は長いようで、あっという間の8日間であった。渡航前の天気予報では、後半雨の予報であったが、幸いにも天気に恵まれた8日間であった。
飛行機で、5時間程で成田空港へ到着。入国の際、ホテルで作っていただいた、サンドイッチを成田空港で没収された場面もあったが、無事に入国審査、税関申請を済ますことができた。
飛行機の遅れもなくスムーズに到着できたため、成田空港から上野駅まで、順調に到着。上野駅で1時間30分ほど時間調整を行った。佐久平駅18:15分到着。久々の佐久市に住み慣れた地に降り立ち、やっぱりほっとした。改札の外には、自分たちの出迎えのため、中澤実行委員長、春原氏(佐久市・モンゴル親善協会 会長)、生涯学習課職員、研修生の保護者、歴代の引率者といった懐かしい顔ぶれが見え、帰ってきたんだなと実感した。
早速、帰着式を行った。温かい出迎えを受け、それぞれの家庭へ帰宅した。旅の疲れから、帰りの新幹線の中で爆睡している研修生、レポートをしたためる研修生の姿が見受けられた。引率責任者として、無事子どもたちを親元へ帰すことができ安堵した。
4 おわりに
8日間に渡って行われたモンゴル国での本研修は幕を下ろした。
研修生は慣れない異国の地モンゴルで、言語の違い、食生活の違い、トイレ事情の違い、見知らぬ外国人宅でのホームステイと数々のストレスを感じたことだろうと思います。しかしながら、研修生たちは、温かいホストファミリーの歓迎、現地スタッフ及び日本旅行のスタッフのサポート受けながら、誰一人体調不良を訴える者もなく、大きな怪我をする者もなく無事に研修を終えられたことは、引率者として安堵の一言に尽きる。
また、帰国後の8月14日(木曜)、「FMさくだいら」において研修報告を行った。その際、久々に会う研修生たちが、FM放送の中で目を輝かせながら、はきはきとアナウンサーとの会話をしている姿をみて、8日間の研修が子どもたちを一回りも二回りも大きく成長させたと感じた瞬間だった。
彼らの今後の人生において、待ち受けるであろうどんな困難にぶち当たっても、今回経験した数々の困難な経験がきっと役に立つものと確信しております。
結びに、このような機会を与えていただいた事に厚く御礼を申し上げるとともに、この研修を成功に導くために、影となり日向となりご尽力いただいた「ふるさと創生人材育成事業実行委員会事務局(生涯学習課)の皆様はじめ、副団長の佐藤美奈子氏、日本旅行佐久平サービスの水間氏、栁澤氏、モンゴル国の現地スタッフの方々など、お世話になった全ての皆さんに心から感謝を申し上げ、筆をおきたい。
お問い合わせ
電話:0267-62-0671(生涯学習係・青少年係)0267-66-0551(公民館係)
ファックス:0267-64-6132(生涯学習係・青少年係)0267-66-0553(公民館係)