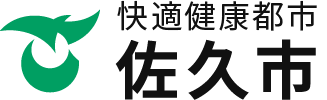令和7年度 中学生海外研修(モンゴル国・エストニア共和国)研修生報告
更新日:2025年9月11日
佐久市では、平成元年に国から交付された「ふるさと創生資金」を「佐久市ふるさとづくり基金」として積み立て、その基金の活用により、次代の佐久市を担う人材を育成するための「佐久市ふるさと創生人材育成事業」を実施しています。中学生を対象とした今年度の海外研修は、姉妹都市であるモンゴル国ウランバートル市スフバートル区とエストニア共和国サク市において実施しました。
今回この海外研修に参加した研修生の感想を紹介します。
また、詳しい研修報告につきましては、ホームページに引率団長の報告を掲載いたしますので、そちらもご覧ください。
なお、研修生の報告につきましては、報告書(冊子)を令和7年3月頃に各地区の支所や図書館、公民館へ配布する予定です。是非ご覧ください。
中学生海外研修(モンゴル国)の概要
この研修は、佐久市の中学生がモンゴル国ウランバートル市にあるスフバートル区を訪問し、遊牧民のゲルや一般家庭でのホームステイ、子ども交流会を通して相互理解を深めるとともに、乗馬体験やゲル作りなどを通してモンゴル国の風土や文化を肌で感じることで、国際的視野を広げることを目的とした研修です。

- 研修生・・・市内中学生8名
- 事前研修・・・8回
- 本研修・・・7月27日(日曜日)から8月3日(日曜日)までの8日間
研修生の感想
(誤字・脱字以外は原文のまま掲載しています。)
浅間中学校 1年 馬場和志
『モンゴル研修で思ったこと・学んだこと』
まず最初にモンゴル研修に参加して思ったことについて紹介報告します。1つ目は、チンギスハーンがモンゴルの英雄だということが本当に伝わった事です。どこに行ってもチンギスハーンの名前をよく聞いたり、像や絵を見たりしチンギスハーンの事をたくさん見聞きして、また、チンギスハーンがみんなから選ばれてリーダーになった話を聞きました。チンギスハーンはモンゴルの人々にとって誇りだということが分かりました。2つ目は、車が多く車社会だということです。とても車が多かったのですが、「これでも夏休みで少ない」と言われて驚きました。しかも日本の車が多かったです。乗用車だと、ほとんどの車が日本車だったので、日本の車の技術が高いと感じました。そしてモンゴルでは、あまり電車が普及していないことにも驚きました。モンゴルでは草原が広がっているから電車がよくあると思っていました。しかし実際にはモンゴルでは電車があまり普及していなかったので、渋滞をなくすためにも電車を広めていけたらいいなと思いました。3つ目は、中国語や韓国語をよく見ることについてです。モンゴルは中国と韓国と経済交流が盛んなんだと思いました。
次に研修で学んだことについて報告します。モンゴルの食事、モンゴルの人と交流・モンゴル特有の建物ゲル作りの体験をしました。これらを通して日本とモンゴルの文化の違いを学ぶことができました。また言葉が通じないけれど、モンゴルの人達と触れ合うことで、コミュニケーションはできると感じました。
この研修を通して日本と文化や習慣が違う国がいることと体験したので、外国の考えを知る時にその国の文化、習慣も知るようにしたいと思います。
浅間中学校 2年 高見澤水仁
『モンゴル研修で学んだこと』
僕はこの研修でモンゴルに住む人たちに学んだことが2つあります。
まず1つ目は、人との距離感が近いということです。例えば、エレベーターに入る時、日本ではスマートフォンを見ている人や家族・友人と話している人をよく見かけます。ところが、モンゴルではエレベーターに乗る時、ほとんどの人が乗っている人にあいさつをして、知らない人同士で話し合っている人にあいさつをして、知らない人同士で話し合っていました。また、モンゴルのホームステイ先の子はカートが段差に引っかかって困っている人を見るとすぐ助けました。
2つ目は、努力を惜しまない姿です。これはモンゴルに住む人達全員ではなく、スフバートル区の研修生に感じました。僕のお世話になったホストファミリーの子は、学年は同じでしたが英語は僕よりも上手でした。理由を聞くと、好きなユーチューバーが英語で話すからだそうです。
僕もモンゴルに住む人達を見習い、やりたいこと、なりたいもののために努力できるようになりたいと思いました。
浅間中学校 3年 久保仁乃
『モンゴルに行って感じたこと』
私は今回初めて海外に行きました。私にとって日本を出るということはとても大きな挑戦でした。でも仲間たちと研修を重ねて7月27日モンゴルへ行ってきました。研修を通して印象的だったこと4つを紹介します。
まず1つ目はやっぱり言語です。モンゴルは基本モンゴル語で日本語はもちろん英語も通じないこともたくさんありました。それでもなんとかコミュニケーションをとろうと、アプリやジェスチャーで会話したことが印象的でした。
2つ目は食事です。日本と違って全く野菜がありません。基本は肉やチーズがメインでした。肉は羊肉が主流で少しクセがありました。チーズは「モンゴリアチーズ」というのがあってモッツァレラチーズに近い味でとてもおいしかったです。ちなみに私の一番のお気に入りはミルクティーで日本と違って甘くないのがすごく好きでした。
3つ目は自然です。2・3日目にゲルに泊まったとき本当になにもない草原の中で暮らしていて「世界はこんなに広いんだ」と実感しました。360°草原で山や木もないから空もすごく広く見えて本当に感動しました。時計がないので時間を気にせず好きなだけ遊べて「日本じゃ絶対にできないな」と思いました。
最後は人と人とのつながりです。7日目の夜、ホストファミリーとのお別れのとき私は泣きそうになりました。なぜなら「別れたくない」「もっと一緒にいたい」そう言ってくれたからです。一週間という短い間だったけど本当の家族のように接してくれて「言葉が通じなくても仲良くなれる」そう実感しました。今回の旅で人生で一番大切なのは人とのつながりということにあらてめて気づくことができました。
野沢中学校 2年 桜井優豪
『初めてのモンゴル』
私は今回初めて海外研修に参加して感じ、一番心に残っている事を書いていきたいと思います。
今回のモンゴル研修に参加して一番楽しかった事は、キャンプ場での、子ども交流会です。初めて研修生全員が、集まった瞬間でした。このみんなで、まず鬼ごっこをしました。日本の人達でやっていたら、モンゴルの子達もいっしょにやり初めて、とても楽しかったです。そのあと、弓矢をやったり、マウンテンバイクに乗ったりしました。子ども交流会では、まず佐久市紹介をしました。ぼくは佐久市の概要を説明しました。当日は、モンゴルのみんなに伝わるかとても心配になりました。でもうまく説明できたので、良かったです。次に乗馬をしました。初めて乗った事もあって難しかったけれど、モンゴルの人達はしっかり乗りこなしていて、すごいと思いました。ぼくも一応一人で操れたけど、途中からで、モンゴルの子達は一人で、最初から一人だった子もいたのですごかったです。
次にゲル作りをしました。泊まったゲルよりは小さかったけど、達成感があり、現地の人たちは、2人で建てると聞いて驚きました。
次に、日本のゲームを教えました。ぼくがだるまさんがころんだを教えて、うまく教えられ、遊べたので良かったです。
今回、初めて海外へ行き、初挑戦が多かったけど、とても良かったです。今後も海外に行くチャンスがあったら、どんどん参加したいです。
野沢中学校 2年 平林芽彩
『モンゴル研修を通して』
私がこの研修に参加した理由は、遊牧民の生活や乗馬を体験してみたかったからです。
遊牧民宅では、二日間過ごしました。ゲルは狭いというイメージでしたが、実際はそんなことはなく、とても広々とした空間で、タンスやベッドなど様々なものが置いてありました。遊牧民の人たちが工夫して生活していることを知って、知恵がすごいなと思いました。
ゲルの中では、羊のくるぶしの骨を使ったゲームなどをしました。スマホの翻訳を使って、ルールを教えてもらいました。骨を投げてその位置でコマが進んでいくゲームは、ルールは簡単なものでしたがとても楽しく盛り上がりました。ゲルを自分たちでも組み立てました。私は真ん中の柱を持ちました。周りから屋根を支える棒を突き刺すのですが、うまく刺さらず真ん中にいる私の腕や頭に当たって痛かったです。でも、これを遊牧民の人は二人で作ってしまいます。遊牧民の人たちの工夫の詰まったゲルはすごいなと思いました。
乗馬体験では、乗る前からとてもわくわくしました。自分で馬に乗って、モンゴルの壮大な草原の中を走りました。想像以上に楽しくて、乗馬することが出来て良かったです。そのあとにラクダにも乗りました。ラクダは後ろの足から立ち上がるので後ろのこぶの方へもたれかかって立ち上がりました。馬よりも安定感がなく、ちょっと段差があるところでとても揺れて少し怖かったです。馬は日本でも乗る機会がありますがラクダはないので、良い経験になりました。
今回の研修でとてもたくさんモンゴルの事を知ることが出来ました。日本では経験することが出来ない、数々の工夫がなされた遊牧民宅へのホームステイやラクダに乗る事など、五感を使った貴重な経験ばかりでした。一生忘れられないことでしょう。この研修に関わってくださった皆様ありがとうございました。
中込中学校 2年 江刈内めい
『しげきいっぱいの海外研修』
海外研修に参加して私は、様々なことを学び、経験することができました。全八回におよんだ事前研修、実際にモンゴルで過ごした八日間、それぞれで学んだことを紹介したいと思います。
まず、事前研修で学んだことは、自分で考え動くのは大切だということです。グループ活動では、自ら積極的に声をあげていかなくてはいけません。また、机や椅子の準備・片付けも自分から動かなければいけません。当たり前のことではありますが、初めて会いまだあまり日が経っていない研修生のメンバーと話し合ったり、協力することは思いのほか勇気のいることでした。しかし、そんな中でも積極的に動く研修生7人を見て私も、自分で考えて自分から動き出さなければいけないなと改めて気付き、学ぶことができました。
次に、八日間のモンゴル研修で学んだことは、とにかく笑顔で接することが大切だということです。ホストファミリーのお父さん、お母さんやペアの子が英語で話しかけてくれても正直、理解できないということが多かったです。また、ゲルで過ごしたときには遊牧民の方々とコミュニケーションを取るのが難しかったです。しかし、言葉が分からなかったとしても、笑顔で自分の言える単語を頑張って伝えればどうにかなります。とにかく下を向いて、ボソボソと言っても人に伝わりません。苦しくても笑顔で接すれば相手も自然に笑顔になり、なんとなくでもコミュニケーションをとることができます。『世界の共通言語は笑顔』本当にその通りだと思います。実際にモンゴルで過ごしたことで学ぶことができました。
私は、海外研修に参加したことでたくさんのことを学ぶことができました。人として成長できたとも思います。とても良い経験をすることができました。ありがとうございました。
臼田中学校 3年 兒野夢羽
『モンゴルと日本のお店の違いについて』
私は、モンゴルと日本のお店やお店以外にもどこが異なるところなのか、一緒なのか気になっていたので研究課題として調べてきました。
一緒のところはナイキやプーマ等のスポーツメーカーのお店やKFCがあったところです。日本とは違うけれどキャラクターグッズもありました。異なるところは、お店はデパートが基本で中にスーパーや新車を売っていたり、フードコートやUFOキャッチャーなど様々なお店がありました。デパート以外にも露店やキッチンカーなどもありました。気づいたところは、日本車が多い事や、日本語しか書いていない商品、例えばスーパーには野菜生活。ゲルにはマスク、ホームステイ先にはゴマドレッシングがありました。日本語しか書いていないのにどうやって買っているのか疑問に思いました。最近流行っているNICIのぬいぐるみキーホルダーも売ってありました。
お店以外に違ったところは、道路は右側通行、学校は小学校5年、中学校4年、高校3年の計12年生となっている事、電気は石炭でできていることや就寝時は、日本はねまきで寝るけれど下着で寝る人が多い事が分かりました。その他ゲルでは、バイクはヘルメットなしで乗っていることや犬を飼っていることが多く、日本とは違い番犬的な存在で噛みつくので危険ということやホームステイ先ではシートベルトをするのは運転手だけという事や、お昼にハンバーガーを食べに行った時、みんな使い捨て手袋をつけて食べていることに驚きました。
モンゴルは、日本と全部違うことばかりで驚きました。日本よりも発達しているところもあれば発達が遅れているところもあり、とてもたくさんの違うところを実際に見て調べてくることができました。
佐久長聖中学校 1年 星野紗希
『モンゴルの食』
私が特に興味があった食のことを中心に報告したいと思います。ホストファミリーの家では韓国料理や中国料理、デザートには果物も出ました。お米も食べました。日本とさほど変わらない食生活で予想とは違ったので驚きました。研修生と日本の豚骨ラーメンを食べたり、ノミンデパートの中にも日本のチェーン店ペッパーランチがあったり、街中にも寿司屋を見つけました。想像していたよりも色々な国の料理を食べていることに驚きました。そしてモンゴルは意外なことに韓国との結びつきが強いようでコンビニはほとんど韓国資本で、K-POPショップでもたくさんありました。
ホストファミリーと最初は言葉の壁があってうまく会話をすることができませんでした。ですがスマホの翻訳機能を使ってお互いの好きなことを話していくうちにいつの間にか言葉の壁を乗り越えていました。自然に笑顔も出てきてホストファミリーと話をするのが本当に楽しかったです。
遊牧民宅での食事で印象的だったのは小籠包のような「ボーズ」です。それは、中国の包子から影響を受けて、モンゴル独自に発展してきた伝統的な料理だそうです。包むのを手伝いました。きれいな形にするのがとても難しかったです。食べた瞬間中から肉汁があふれ出てきてとてもおいしかったです。また羊肉入りの野菜スープも出ました。モンゴルは気候的に野菜や果物が育ちにくいので乳製品や肉の食事が多いと聞いていましたが、遊牧民の生活の中でも野菜を使った料理が出てくることに驚きました。気になったので家に帰って調べてみたところ、野菜は中国やロシアからの輸入品がほとんどで都市部の人は食べますが、伝統的にはあまり食べないそうです。つまり野菜スープは遊牧民宅の人が外国人向けに作ってくれたのではないかと思いました。馬乳酒もいただきました。一口飲んだのですが、動物や草の香りが強く癖がある感じでした。なじみのない味で、面白いなと思いました。馬乳酒作りも体験させてもらいました。大きな入れ物の中に馬乳が入っていてそれをかき混ぜて馬乳酒を作ります。ただかき混ぜるのではなく、上下に動かし空気を入れるように泡立てます。それが以外に難しく大変で、腕が筋肉痛になりました。
今回の研修を通して外国の人とのコミュニケーションの楽しさに気づけました、そして、「日本ほど発展していないから食文化は全然違うのではないか?」など、モンゴルの食への偏見や思い込みが実際に行ってみてぬりかえられ、世界のグローバル化、均一化が進んでいることを実感しました。
多くの日本人がモンゴルを訪れ、魅力を知ってもらえるようになってほしいです。貴重な経験を与えてくださった方々に感謝しています。

中学生海外研修(エストニア共和国)の概要
この研修は、佐久市の中学生がエストニア共和国サク市を訪問し、一般家庭でのホームステイや現地学生との交流を通して相互理解を深めるとともに、学校訪問やエストニア国内見学などを通してエストニア共和国の風土や文化を肌で感じることで、国際的視野を広げることを目的としています。
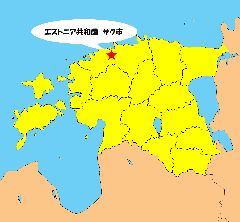
- 研修生・・・市内中学生8名
- 事前研修・・・8回
- 本研修・・・7月28日(月曜日)から8月4日(月曜日)までの8日間
研修生の感想
(誤字・脱字以外は原文のまま掲載しています。)
野沢中学校 2年 江村希
『この研修に行ってみて』
私はこの研修に行ってみて成長したことがたくさんあります。
まず1つ目に「人と交流する力」がついたことです。私は、自分からあまり相手に話しかけることができず、この研修で国も人種も言葉も違う人達と交流していく中で、自分から話しかけたり交流したりすることができるようになってきました。メンバーとも仲よくすることができました。
2つ目は「コミュニケーション能力が上がった」ということです。言葉がでてこずにフリーズしてしまうことも少しはありましたが、研修の前よりもこの能力は格段に上がったと思いました。
3つ目は「決断力が高まった」ことです。今回の研修では自分で選択する場面が多かったです。自分のやりたい事、言いたい事を「どちらでもいい」ではなく、ちゃんと自分の意見を言えるようになりました。
今回の研修を通し、国が違う人々と関わることの楽しさと大切さ、日本とはまた別の文化や町並み、歴史について見たり聞いたりして学ぶことの重要性を学ぶことができました。また、自分が足りていないと感じる能力を成長させることもできました。この研修に行って自分は変われたと思いました。エストニア研修に行って本当に良かったです。
臼田中学校 2年 木本怜
『エストニア研修で思ったこと』
今回のエストニア研修では、日本とちがう文化や生活をたくさん体験することができました。飛行機での移動はとても長く大変でしたが、現地につくと涼しくすごしやすい気候で安心しました。サク市の田舎の風景は佐久市に似ていましたが、料理などは全然違いました。キャンプ場では、ボートをこいで人工の山に登り、大変でしたが山頂の景色が綺麗でした。首都タリンでは石造りの建物や石畳の町並みがヨーロッパらしい風景でした。学校見学では広い体育館やカウンセラーの部屋、有料のロック式のロッカー、ビリヤード台、ダンスの教室まであり、日本の学校との大きな違いに驚きました。さらに建設費が五百四十億円と聞いて信じられませんでした。ホームステイでは広い家や庭、サウナなど日本にはない生活を体験しました。ホストファミリーはとても優しく、快適に過ごせました。また、ロシア大使館前では戦争反対のメッセージがたくさん書かれていて、今のヨーロッパの現状を実感しました。六日間の研修はあっいう間でしたが、文化のちがいやつながりの大切さを学びました。この経験を生活や将来に活かし、また海外で挑戦してみたいと思いました。
臼田中学校 3年 井出華
『エストニア研修を通して得られたこと』
今回のエストニア研修では、英語で積極的に話す力をつけ、自分から行動する自信を身につけることを目的に参加しました。また、異文化交流を通して自分の視野を広げたいと思っていました。
最初は「本当に違う国の人と仲良くできるのかな」と少し不安もありました。でも、自己紹介や簡単なゲーム、会話をしてみると言葉が完璧でなくても笑顔や身振り、手振りで伝わることが分かり、すぐに楽しくなりました。思ってた以上に交流って面白いんだと実感できた瞬間です。
もちろん課題もありました。難しい話題になると理解が追いつかず、自分の意見もうまく伝えられないこともありました。事前にもう少し文化や歴史を調べておけば、質問ももっと積極的にできたのかなと思います。それでも、間違えても挑戦して伝えようとすることが大切ということを学べたのは大きな収穫でした。
今期の研修で特に感じたのは、エストニアは距離的には遠いけれど、日本と完全に違う国というわけではないということです。文化や生活の違いはあっても、笑ったり驚いたりする場面は同じで、そうした共通点に触れられたのが嬉しかったです。加えて、日本には少し閉鎖的な雰囲気がありますが、エストニアの自由に挑戦できる環境で過ごす中で、周囲にあわせることへのこだわりが自然と薄れていきました。
今回の経験をきっかけにエストニアだけでなく、他の国のことももっと知って、自分の世界をもっと広げたいと思いました。挑戦する楽しさや、違いを楽しみながら共通点を見つける面白さを学べました。今回の研修がもっと世界を知り、世界で活躍したいというきっかけになりました。
関係者の皆様、貴重な体験をさせていただき本当にありがとうございました。
佐久長聖中学校 1年 寺島澪
『エストニア研修で広がった視野』
私が研修に参加したきっかけは2年前に同じ研修に姉が参加したことでした。うちにホームステイをしたエストニアの子ケルトはとても親切にしてくれたので一緒にたくさん遊びました。その時の生活習慣や食べ物の微妙な違いが気になり、エストニアに興味を持ち始めてこの研修に参加しました。
今回の研修で印象に残っていることが2つあります。
まず1つ目は、エストニア人についてです。最初、私は外国の人に対してこわいイメージがありました。けれど実際に関わってみると、すごく親切な人ばかりでした。まず、はじめて会うと笑顔で歓迎され、荷物を運ぶのを手伝ってくれます。目が合うと必ずほほえみを返して進んで話しかけてくれます。なのですぐ仲よくなることができました。エストニアの人々は背も高く、同い年なのにペアの子のほうが大人っぽかったです。
2つ目は、タリン旧市街についてです。タリン旧市街地に行く前までは、山がないだけで日本とあんまり景色が変わらないと思っていたんですが、タリン旧市街はすごくメルヘンで、西洋のおとぎ話に出てくるようなところでした。ヨーロッパ風の建物がずらりと並び、見たことのないバイオリンに似たような楽器を街中で披露している人がいたり、かわいいキーホルダーなどがたくさん売っているお店もたくさんありました。タリン旧市街はすごくにぎやかで建物もおしゃれなので上から見た景色は最高でした。
この研修を通して私はエストニアがすごくすてきな所だということを知ることができました。正直最初は行きたくないという気持ちもありましたが、今はもっとエストニアと関わってみたいと思いました。それと同時に他の外国も気になるようになりました。これからもいろいろな挑戦をしてみようと思います。
佐久長聖中学校 2年 小川真央
『エストニア研修を通して』
私はこの研修を通して、一生の思い出になるような体験をいくつもしてきました。その中でとくに印象に残った2つを紹介します。
まず1つ目は「白夜」です。日本で生活をしていたら白夜を体験するなんてありません。なので、どのような生活をしているのかとても気になっていました。22時30分頃まで明るいので22時までサウナに入っている人や、カードゲームをしたり、日付が変わるまで話していたりと、とにかく夜寝るのがとても遅かったです。次の朝は大丈夫かなと考えたりしましたが、夜が遅いので朝も遅いです。朝食は8時~9時の時間でした。まるで休日のような生活の仕方でした。
2つ目は「人柄の良さ」です。日本人に少し性格が似ている気がしました。私達もエストニアの人達も心を開くまでに少し時間はかかったと思いますが、とても仲良くできたと思います。エストニアの人達と話すのにとても緊張していましたが、ホストファミリーが簡単な英語で話しかけてくれたおかげで、すぐに緊張がほぐれて会話がたくさんできました。私が困っていればホストファミリーが助けに来てくれました。そのおかげで不安などは一切ありませんでした。この研修を楽しく行ってこれたのは、ホストファミリーのおかげと言ってもいいはずです。
今回の研修で、普段の生活では決して得られないような体験をたくさんすることができました。この経験を通して、もっと積極的なことに挑戦していきたいと考えるようになりました。今回の研修で学んだことを、これからの生活に生かしていきたいと考えています。そしてまたいつか、エストニアに行きたいと思います。
佐久長聖中学校 3年 小平京花
『エストニア研修を通して』
私は、今回のエストニア研修を通して、異文化交流の良さを知りました。
約2か月間の事前研修と8日間の現地研修とでは、学べたことや見聞したことに大きな差を感じました。資料を見るのではなく、目で見て肌で感じることこそが現地研修の良さだと思いました。エストニア人の人柄、優しさは現地でしか感じとることができない事の1つだと思いました。特に、私の拙い英語にも最後まで耳を傾け、理解しようとする姿勢に深く感謝の気持ちを覚えました。そして、何度も聞き返す、意見の明確化の重要性を改めて感じました。
また、私たちは今回の研修でホームステイをしてきました。ホームステイを体験することで、インターネットや本からでは学ぶことができない生きた言語表現や文化に触れることができると私は感じました。そのため、日本の文化と比べて大きな違いを持つエストニアやヨーロッパの文化に、ホームステイを通して強く惹かれました。自分の視野の広がり、文化を学ぶことの楽しさを改めて実感しました。
今回の研修で得た気づきや学びを今後の生活や学習、将来に活かしていきたと思います。そのために日頃から積極的に異文化理解や言語学習に取り組んでいきたいです。
佐久長聖中学校 3年 小山顕
『海外研修で楽しかったこと』
僕が今回の海外研修に参加して楽しかったことを3つ紹介します。
1つ目は、エストニアの生徒と交流したことです。最初はとても緊張していたし、英語で話せるか不安でした。でも、話しかけてくれて、とても親切にしてくれて仲よくなって良かったです。一緒にいろんなゲームで遊べたのがとても楽しかったです。
2つ目は、ホストファミリーと買い物や観光をしたことです。大きなショッピングモールンにはたくさんのお店があり、回るのがとても楽しかったです。休日には、湿地帯へ連れていってもらいました。展望台に登ると、今までに1度も見たことのないような広さの林でした。釣りにも連れて行ってもらいました。そこで塩焼きにした魚はとても美味しかったです。
3つ目は、タリンの街をまわったことです。日本では見れない風景が広がっていました。とてもカラフルな建物が並んでいて、すごく可愛かったです。そこでは、何回かレストランで昼食を食べたのですがどれもおいしかったです。
また、クルトナ学校でのお別れ会には、僕が5歳の頃、家にホームステイで受け入れたマリアが会いにきてくれました。久しぶりに会えてとてもうれしかったです。今回の研修では、そこでしかできない経験や出会いがたくさんありました。まだ帰りたくないと思えるぐらい楽しい研修でした。
佐久長聖中学校 3年 西澤唯花
『エストニアの思い出』
エストニアを訪れて一番の思い出は、ホストファミリーが家族の一員のように優しく接してくださったことです。「エストニアでの8日間をずっと忘れないで覚えていてほしい。」とパパとママは様々な所へ連れて行ってくださいました。夜のタリン市街、音楽フェス、海、ゴルフ、遊園地、植物園、TVタワー、お買い物、すべて満喫することができました。朝食には、美味しいフルーツが盛りだくさんでした。庭にはたくさんのラズベリーがあり、たくさんいただきました。エストニアのご飯はどれも美味しかったです。私が持って行ったお土産を説明しながら一緒に食べて会話をしたのも楽しかったです。日本のお菓子はどれも美味しかったようですが、一番気に入ったのは、緑茶とお煎餅でした。フリーズドライのお味噌汁をそのままかじり出したり、プラスチックの袋が開けられなくてナイフで刺して開けたのには、ユニークすぎて笑ってしまいました。優しくて明るくて愉快なウルマス家で過ごせて、忘れられない体験になりました。
エストニアで出会った全ての人たちに感謝の気持ちでいっぱいです。また、この研修に携わってくださった皆さん、本当にありがとうございました。
お問い合わせ
電話:0267-62-0671(生涯学習係・青少年係)0267-66-0551(公民館係)
ファックス:0267-64-6132(生涯学習係・青少年係)0267-66-0553(公民館係)