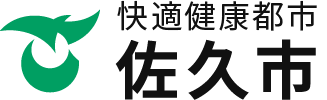帯状疱疹ワクチン接種について
更新日:2025年12月26日
令和7年度より定期接種を開始しました
第65回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(令和6年12月18日)において、帯状疱疹を予防接種法のB類疾病に位置づけることが承認されました。
令和7年度の対象者へは4月に個別通知を発送しました。
※個別通知(接種券)を紛失してしまった場合は、佐久市保健センターまたは各支所で再発行ができます。
持ち物:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
対象者
(1)令和7年度内に下記の年齢になる方
| 年度年齢 | 令和7年度対象者生年月日 |
|---|---|
| 65歳 | 昭和35年4月2日 ~ 昭和36年4月1日生まれ |
| 70歳 | 昭和30年4月2日 ~ 昭和31年4月1日生まれ |
| 75歳 | 昭和25年4月2日 ~ 昭和26年4月1日生まれ |
| 80歳 | 昭和20年4月2日 ~ 昭和21年4月1日生まれ |
| 85歳 | 昭和15年4月2日 ~ 昭和16年4月1日生まれ |
| 90歳 | 昭和10年4月2日 ~ 昭和11年4月1日生まれ |
| 95歳 | 昭和5年4月2日 ~ 昭和6年4月1日生まれ |
| 100歳 | 大正14年4月2日 ~ 大正15年4月1日生まれ |
| 101歳以上 | 大正14年4月1日以前の生年月日の方 |
(2)60歳~64歳の方でヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害により身体障害者手帳1級を有する方
接種期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
※組換えワクチン接種の場合、標準的には2か月の間隔で2回接種するため、1回目を令和8年1月31日までに接種する必要があります。
※令和7年度に定期接種対象となる方は令和8年度以降の接種は任意接種(全額自己負担)となります。この機会に接種をご検討ください。
用いるワクチンと接種回数
| 水痘ワクチン(ビケン) | 帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | |
|---|---|---|
| ワクチンの種類 | 生ワクチン | 組換えワクチン |
| 接種回数 | 1回 | 2回(※) |
※2か月以上7か月未満の間隔をあける(病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。)
※それぞれのワクチンの予防効果や副反応などの詳細は![]() こちら(PDF:370KB)
こちら(PDF:370KB)
接種費用(自己負担額)
- 生ワクチン:2,000円
- 組換えワクチン:6,000円/回(2回接種の計12,000円)
自己負担免除者
定期接種対象者の方で下記の条件に該当される方は、接種費用が免除されます。接種を受ける前に事前申請が必要です。
ア.生活保護法の適用を受けている方(接種時)
イ.市県民税非課税世帯の方
ウ.ヒト免疫不全ウイルスの疾病により身体障害者手帳1級の交付を受けている方
申請場所
佐久市保健センター(健康づくり推進課)または各支所健康づくり推進係
持ち物
- 本人確認ができるもの(保険証または運転免許証、マイナンバーカード等)
- 身体障害者手帳(自己負担免除者ウに該当する方のみ必須)
代理人が申請される場合、接種を受ける方と代理人の方それぞれの本人確認ができるものをご持参ください。
該当する方には、帯状疱疹定期接種予診票(無料券)を交付します。
接種方法
【市内医療機関で接種する場合】
- 接種をご希望の方は、「帯状疱疹定期接種実施医療機関」に予約をして接種を受けてください。
- 接種を受ける際には、接種券(サーモンピンク色の用紙)を実施医療機関に提出してください。
- 予診票は、各医療機関にあります。
【市外医療機関で接種する場合】
- 長野県の予防接種相互乗り入れ事業によって市外の医療機関で受けることができます。予防接種市町村間相互乗り入れ接種医療機関であるか、医療機関にお尋ねください。
- 市外の場合は予診票が医療機関にはありませんので、事前に佐久市保健センター(健康づくり推進課保健予防係)または各支所健康づくり推進係で受け取り、医療機関に予約をして接種を受けてください。
※佐久市発行の予診票がないと全額自己負担になります。
- 接種を受ける際には、接種券(サーモンピンク色の用紙)を実施医療機関に提出してください。
![]()
![]() 予防接種市町村間相互乗り入れ接種医療機関(外部サイト)(長野県医師会を通じて契約している医療機関)
予防接種市町村間相互乗り入れ接種医療機関(外部サイト)(長野県医師会を通じて契約している医療機関)
関連情報
過去に帯状疱疹予防として任意接種(自費での接種)を受けたことのある方
前回接種から一定時間が経過し、ワクチンの有効性が低下したと考えられる場合など、医師が予防接種を行う必要があると判断した場合は定期接種を受けることができます。接種を受ける必要性の判断については、過去に帯状疱疹ワクチンを接種した医療機関や、かかりつけ医へご相談ください。
帯状疱疹とは
水痘(水ぼうそう)発症後、神経節などに潜伏感染しているウイルスが加齢や疲労、ストレス等の何らかの原因で免疫が低下した際に再活性化し、体の片側に水ぶくれを伴う赤みが帯状に広がります。痛みを伴うことが多く、3~4週間ほど続きます。
また、皮膚の症状が治った後も、帯状疱疹後神経痛(PHN)と呼ばれる長期間にわたる痛みが続くこともあり、数か月、ときには数年にもわたり強い痛みが残ることがあります。50歳以上では、帯状疱疹を発症した人の約2割が帯状疱疹後神経痛に移行するといわれています。
帯状疱疹の予防(日常生活での留意点)
免疫機能を高める
帯状疱疹の発症には、免疫機能の低下が関係していることが知られています。加齢や疲労、ストレスなどによって免疫機能が低下すると、潜伏していた水痘・帯状疱疹ウイルスが再び活性化しやすくなります。
また、健康な高齢者でも、加齢により免疫機能が低下していると考えられます。日頃から十分な休息をとりながら免疫機能の維持を心がけ、免疫機能を低下させる疲労やストレスのない規則正しい生活を送りましょう。
バランスの良い食事と適度な運動、睡眠
一般的には、偏った食生活や運動不足、睡眠不足などが、免疫機能を低下させてしまうと言われています。バランスの良い食生活や適度な運動、質の良い睡眠といった規則正しい生活をすることが重要となります。
食事では、さまざまな栄養素をバランスよく摂ることを心掛け、暴飲暴食は避けましょう。
運動については、体温が少し上がる程度の散歩やウォーキングなどがおすすめです。また、日光を浴びることも免疫機能アップにつながります。逆に激しい運動や長時間のトレーニングは、免疫機能を下げてしまいますので注意が必要です。
睡眠は、身体をメンテナンスするうえで重要な働きをしていますので、質のよい睡眠をとることを心掛けましょう。
この他にも、音楽を聴く、テレビや映画を観る、瞑想や入浴など、自分なりのストレス解消法を見つけておくとよいでしょう。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種法に基づく予防接種後に、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料が支給されます。
給付申請の必要が生じた場合には、健康づくり推進課保健予防係(佐久市保健センター)までご相談ください。![]()
![]() 予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)(外部サイト)
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)(外部サイト)
担当係:保健予防係
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
電話:0267-62-3196(健診推進係)、0267-62-3527(保健予防係)、0267-62-3189(健康増進係)、0267-63-3781(口腔歯科保健係) 、0267-62-3524(保健医療政策係)
ファックス:0267-64-1157