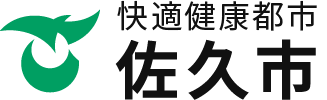「令和7年度 水田フナ養殖技術講習会」の閉講式を実施しました
更新日:2025年10月3日
目的
佐久市では、昭和50年代から、徐々に水田でフナが養殖されるようになりました。
平成17年は年間約20トンの生産量がありましたが、近年は減少傾向であり、水田でフナを養殖する技術の継承が問題となっています。
そこで、佐久地域の文化である水田フナ養殖による小ブナの生産拡大と技術の継承を目指し、実践的な講習を開催する運びとなりました。
以下に実施した講習会の様子をご紹介します。
第7回講習会(閉講式)
講習会に参加した感想(1)
講習会に参加した感想(2)
講師からの講評(1)
講師からの講評(2)
閉講式では、講習会の内容を振り返りながら、報告を行いました。
3名の講習生から、講習会に参加した感想をお話ししていただきました。
水田でフナを養殖することの難しさをはじめ、講習会を通して今まで知らなかった知識・技術を学ぶことができたこと、次年度以降について、小ブナの養殖に携わる方法等を模索しているという発表がありました。
最後に、講師のお二方に講習会の講評をいただき、今年度の講習会は修了となりました。
- 日 時:令和7年9月30日(火曜) 午後2時から午後3時
- 場 所:佐久市役所
第6回講習会(料理講習会)
袋詰めされた小ブナ
生きたままのフナを鍋へ投入
煮汁を全体にかける様子
試食
水揚げされた小ブナの料理の調理方法を学ぶために、今回は料理講習会「小ブナの甘露煮を作ってみよう!」に参加しました。
- 日 時:令和7年9月5日(金曜) 午前10時から正午
- 場 所:道の駅ヘルシーテラス佐久南 体験室
第5回講習会
水田内の溝
音を立て、小ブナを追い込む様子
小ブナの大きさを確認する様子
今シーズン2回目の水揚げ
出荷前の水揚げに関する作業を見学しました。
以下、水揚げから出荷に関するスケジュールについて掲載します。
- 8月30日 水揚げ(1回目)60キログラム
- 8月31日 網生け簀へ移動(フナに泥を吐かせ、大きさを選別する)
- 9月 1日 出荷
- 9月 2日 水揚げ(2回目)
小ブナが袋詰めで出荷販売される様子は、佐久の秋の風物詩です。
いよいよ出荷が始まります。
- 日 時:令和7年9月2日(火曜) 午前6時から午前7時
- 場 所:生産者のほ場
第4回講習会
生産者のほ場見学
小ブナの確認
小ブナの成育状況
座学の様子
今回の講習会は、佐久平鮒部会の現地検討会に同行しました。
前回の講習会から1ヶ月以上経過し、水田のフナも成長がみられ、給餌の仕方も撒き餌から置き餌に切り替わりました。
水中の植物プランクトンは、昼間は光合成により水中に酸素を補給しますが、夜間は逆に酸素を消費します。水温が高くなる7~8月は、夜になると酸素不足になりやすいため、昼間は止水でもよいそうですが、夜間は水田へ注水した方がよいと学びました。
そのため、給餌にも注意が必要で、フナが摂取した飼料を消化するため、必要とする酸素量が増加します。フナが満腹状態で夕方を迎えるのは危険であることから、高水温期の給餌は午前中1回が望ましいそうです。
フナは酸素欠乏に比較的強い魚ですが、水中の酸素が極端に少なくなると水面に浮上して空気と水を一緒に吸い込もうとして口をパクパクと開閉します。このような行動を「鼻上げ」といいます。鼻上げが起こるのは、水中の酸素が極めて少なくなっている証拠であり、極端な場合は死に至ったり、大きなストレスとなって魚病の発生と蔓延につながることを学びました。
9月の水揚げに向けて、着々と準備が進んでいることが分かりました。
- 日 時:令和7年7月22日(火曜) 午前10時から正午
- 場 所:生産者のほ場
第3回講習会
 仔魚(ふ化から5日後)
仔魚(ふ化から5日後)
 水田の額縁飼育
水田の額縁飼育
 餌の種類
餌の種類
 給餌の様子
給餌の様子
第3回の講習会は、生産者のほ場を見学しました。
水田飼育の準備から、親ブナの産卵、その後のスケジュールの説明を受けました。
産卵~ふ化については、親ブナを水田に放して、水田で卵を産ませる方法と親ブナを生け簀で管理し、卵を産ませ、卵を水田に移し、ふ化させる方法を学びました。
水田の仔魚(しぎょ)はふ化して、4~5日ということで、まだまだ小さく、餌付けはこの日から開始とのことでした。
また、餌の種類についても学びました。
以下、主なスケジュールを掲載します。
- 4月中旬 水田に有機肥料をまく
- 5月15日 代かき
- 5月18日 田植え
- 5月20日 親ブナの配布、水田の額縁に野菜のクズ、鶏糞をおく
- 5月27日 親ブナを生け簀に放す
- 5月28日、29日 主に朝方に卵を産む
- 5月29日 卵を水田に入れる
- 6月2日 ふ化
- 6月6日 餌付け
- 日 時:令和7年6月6日(金曜) 午前10時から正午
- 場 所:生産者のほ場
第2回講習会
親ブナ
親ブナの計測中
親ブナの説明
雌雄のフナ
第2回講習会は、長野県水産試験場佐久支場で、親ブナの配布の様子を見学しました。
毎年5月20日前後に、県水産試験場で育てた親ブナを、生産農家などへ水田養殖用として配布しています。今年は昨年同様に、1キロ当たり1,600円で販売し、生産者は持参した容器にオスとメスの親ブナを入れて、持ち帰っていました。
講習では、親ブナの配布を見学した後、親ブナについての説明を受けました。親ブナの体調は15~20センチ、重さ70~80グラム。雌雄を判別する方法として、産卵期が近付くと、オスのフナのえら表面に、白いポツポツしたものが見られることを学びました。
今年度の配布には30人余の生産者に400キロが配布されました。
- 日 時:令和7年5月20日(火曜) 午前10時から午前11時
- 場 所:長野県水産試験場 佐久支場
第1回講習会
 開講式(1)
開講式(1)
 開講式(2)
開講式(2)
 座学(1)
座学(1)
 座学(2)
座学(2)
水田フナの養殖に関心があり、技術・知識を学びたい方にお集まりいただき、講習会の開講式及び座学講習を行いました。
今年度は3名の受講生と一緒に、熟練した技術を持つベテラン生産者や県水産試験場職員などを講師に招き、水田の準備から水揚げまでの飼育期間を通した実践的な講習を開催します。
開講式では、受講生に講習会で得たいものを、それぞれ語っていただきました。
座学講習では、フナ養殖の歴史から飼育のあらましまで、お話がありました。水田フナの歴史は50年と、鯉の養殖に比べると短いことや(1842年の江戸時代)、年々フナの生産量が減少傾向であることなど、水田フナに係る総論を学びました。
- 日 時:令和7年4月30日(水曜) 午前10時から午前11時
- 場 所:佐久市役所
講習内容
佐久市内でフナを養殖する農家の生産活動(産卵から水揚げ、出荷に至る全過程)に参加し、作業を実際に行いながら、水田フナ養殖技術を学びます(過去の講習会)。
講習期間
令和7年4月下旬から9月下旬予定(平日に実施)
募集要件
水田で行うフナの養殖に興味があり、生産活動に参加してみたい方
講習会に関するお問い合わせ先
佐久市役所 経済部 農政課 農業生産振興係
〒384-8501 佐久市中込3056
電話:0267-62-3203
ファックス:0267-62-2269
水田フナ養殖とは
水田フナ養殖とは、水田を活用して、フナを5センチ前後の大きさまで育てる養殖方法です。
歴史
清らかな水が流れる千曲川沿いの桜井、跡部、中込地域等において、かつて水田で水稲と一緒に鯉を育てる「稲田養鯉(とうでんようり)」が盛んに行われており、フナは副産物として収穫されていました。
その後、鯉はため池等で飼育されるようになり、現在では稲田養鯉は廃れましたが、水田転作の進展とともに昭和53年頃から徐々にフナが水田で養殖されるようになりました。
養殖の流れ
- 産卵・孵化(5月):水田に産卵場を作り、親ブナ(卵を産ませるために大きくしたフナ)と水草を入れます。1日から2日の間にフナが水草に卵を産むので、卵のついた水草を産卵場の外に出し、孵化させます。
- 飼育(6月~9月):餌を与える(給餌)、水草を除去する、水位・水温の調整等の管理を行います。
- 水揚げ(9月):体長4センチから7センチを基準として、フナの水揚げを行います。
出荷販売及び料理方法
佐久市では、全国的にも珍しく、生きたまま5センチ前後の小ブナが袋詰めで出荷販売されます。
佐久市では醤油と砂糖で、甘辛く煮付けた甘露煮でいただく方法が一般的です。
また、フナと一緒に育てた米は安全安心な「フナ米」として、関西地域を中心に高い評価を受けています。