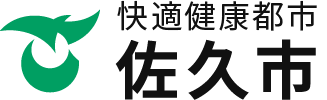記者会見(令和7年8月20日)
更新日:2025年8月25日
令和7年8月20日、午後3時30分より定例記者会見を開催しました。
内容
(1)令和7年佐久市議会第3回定例会提出予定議案等の概要説明・・・![]() 資料1(PDF:1,958KB)、
資料1(PDF:1,958KB)、![]() 資料別冊1(PDF:299KB)、
資料別冊1(PDF:299KB)、![]() 資料別冊2(PDF:387KB)
資料別冊2(PDF:387KB)
(2)その他
会見はX(旧ツイッター)のスペース機能で音声配信しました。
質疑内容(要旨)
(1)令和7年佐久市議会第3回定例会提出予定議案について
Q1:記者
第90号の議案より、「学習者用端末および指導者用端末Chromebookの購入について」とあります。今回松本市のキッセイコムテック株式会社に決まったということですが、今までこういったChromebookの関係は、佐久市内の業者への発注が結構多かったと思います。今回の案分を見ますと、県が実施した共同調達という部分があります。やはり県がある程度先導したというか、どういったことなのでしょうか?
A1:学校教育部長
今回のこの件に関しまして、補助要件の中に共同調達に加わることとなっておりまして、県の共同調達に合わせて、今回契約をしています。
A1:市長
補助要件となると、予算等の関係もお高くなるということですね。
Q2:記者
第91号の医療事項に関わる損害賠償について、事故に遭われた方は何歳代の、何歳の方で、女性男性などはわかりますでしょうか?
A2:浅間総合病院事務長
患者様また、患者様ご家族と、個人情報の関係について公開するというような承諾を得ておりませんので、氏名、性別、年齢等については非公表ということでお願いしたいと思います。
Q3:記者
今の関係で補足してお伺いします。介助時の転倒とありますが、これは市側が損害賠償を支払うということをやっています。これは看護をしている側に瑕疵があったという理解でよろしいでしょうか?
A3:浅間総合病院事務長
今回の医療事故についての概要について申し上げます。
市内在住で訪問看護を利用の患者様です。2019年7月に訪問看護時に、具体的にはフットマッサージを行っておりました。その後マッサージが終了後、看護師の方でフットマッサージ機の方から患者様の足を抜くときになります。患者様は車いすに乗っていたということでありまして、足を抜くときに車椅子ごと転倒してしまったという事案でございます。その後CT検査の結果で、外傷性硬膜下血腫を発症しており、転倒がきっかけの可能性があるということでございました。
フットマッサージ開始時においては、足をマッサージ器に入れる際、もう1人看護師が車椅子後方で車椅子を確保しておりました。終了時の足を抜く際には、車椅子を確保しておらず、訪問看護の記録を作成していたという事案でございます。
今回賠償金として医療費134万7,350円を支払うということで、本年7月11日に和解ということでございます。病院としての再発防止策として、以前からもやっておりましたが、訪問前に訪問看護スタッフによる患者および看護内容の確認の徹底。複数人による訪問看護については、それ以上に細かいカンファレンスですとか、実際に訪問看護時には、目視および声掛けによる確認の徹底等、改善を図っております。
Q3:記者
フットマッサージ機の形状というか、スポンと足をはめるものでしょうか?
A3:浅間総合病院事務長
足形をしておりまして、そこへ足を入れるというマッサージ機になります。
Q4:記者
佐久大学の支援金について、具体的にどんなものか、就学支援交付金はどういったものに使うのでしょうか。債務負担行為の設定額などお伺いできますか?
A4:企画部長
この4月1日から、佐久大学が国の高等教育修学支援制度の対象から外れました。国の制度により、収入の要件等によりますが、これまでは授業料の免除、あるいは入学金の免除等そういった制度がございました。それらが受けられなくなってしまったという現状がございます。その現状から、学生を支援して安心して佐久大学で学んでいただくようにすること。また、来年度以降も佐久大学を進学先として選んでいただけるように、現在、大学側は独自で授業料等減免を行うとしているところでございます。それに対し、佐久市としましても、地域医療に必要不可欠な、医療福祉人材を安定的に育成・供給していくというのが大前提として目的として、必要なことだと考えております。授業料、入学金等の免除などの部分に対しまして、昨年度に続き、学生を支援するといった目的の中で行っているものでございます。金額につきましては、該当者すべてということを考えております。収入の額、あるいは、今年から始まりました多子世帯に対してというものです。3人以上扶養している場合には、授業料免除が適応というものです。今年度はそれらを交付するという形で、また来年度以降もそれを推計した上での金額で、11年度までという形でございます。
Q5:記者
条例改正案で、だれでも通園制度に関しまして、これは本格実施に向けた改正という理解でよろしいでしょうか?それとも先行して少し早めに佐久市としてやっていこうこという、どちらかなと思いまして、お願いいたします。
A5:福祉部長
こちらは本格的実施ということです。他市ではもう先行して今年度から始めているところもありますけれども、全国的にもですが、来年度に本格実施ということです。
Q6:記者
病院会計の関係ですが、総額で見るとやや赤字というふうに理解すればよろしいでしょうか。公立病院は結構運営が厳しいというような話もある中で、今回の決算はどういうふうに見ればいいのかなと。お伺いしてもよろしいでしょうか。
A6:浅間総合病院事務長
病院会計につきましては、収入・支出ともそちらに書いてある通りでございます。結果的には、8,254万円ほどの赤字決算ということでございました。昨年同と比べますと、昨年度が3億5,000万円ほどだったということですので、2億7,000万円ほど赤字を圧縮しているという状況でございます。
この主な原因・要因というのが、内科、産婦人科医師の増員によって、診療件数、手術件数等の増加によるものでございます。6年度においては、黒字ではないけども収支は改善できたというふうに考えております。新聞報道等によりますと、公立病院等々多くの病院の中で、赤字を計上しているということです。当院も赤字の病院の一つではありますが、他の病院とは少し違いまして、収支は改善できているということです。黒字に向けて、今後も努力していきたいというふうに考えております。
A6:市長
経営改善プログラムの中にありますが、青木病院事業管理者においては、医師の確保に向けて非常に積極的に取り組んでいます。私も昨年、入院中でしたけれど、一緒に大学病院の方に足を運びました。他県の大学へ私も同行して、医師確保に向けた努力などが功を奏している面もあるだろうというふうに思っております。また救急車の受け入れについての積極的な姿勢というものがあります。ドクターの皆さんはじめ、メディカルチームの皆さんの負担についても心配をしながら、青木病院事業管理者のリーダーシップによって、この改善がなされている。積極的な取り組みをしています。それにより患者さんの期待に応えていく。そういった緊張感を持った事業運営をしていることを、評価をしているところです。
Q7:記者
令和7年度の補正第4号、商工費、物価高騰対策事業者支援、消費喚起促進事業費というものがあります。キャッシュレスポイントの決済のことだと思います。具体的に、以前のお話では、秋口ぐらいからキャッシュレス決済のポイント還元を行っていきたい、というお話がありました。具体的に開始の時期、企画の内容は、ある程度出来ているのでしょうか?
A7:経済部長
キャッシュレス決済に関するポイント還元事業につきまして、6月の補正のときに約1億円の補正させていただきました。さらに国から追加の臨時交付金の措置がございまして、今回新たに4,000万円追加ということです。今回約1億4,000万円で実施するということでございます。
実施時期につきましては、11月の1ヶ月間を予定しています。その時期が一番、年末商戦の前で、ちょうど売上が落ち込む時期、消費があまりないこの時期である。ここで行ってもらうと助かるということがございましたので、今回、11月に行うということでございます。こちらにつきましては事業者支援を目的にしています。制度説明をいたしますと、使った金額の20%をポイントで還元するという制度になります。キャッシュレスの支払いにつきましては、いわゆるPayPayや、d払いなどといったアプリを利用して、ポイントを還元するという事業でございます。
A7:市長
「これは誰のための物価対策ですか」となった場合に、事業者支援、あるいはまた市民への支援、両方の側面があります。両方ありますが、今回については、今、部長が言った通り、事業者支援を銘打っております。現在は物価高騰ですから。どなた様も物価高騰が生活への影響があります。なので、消費者本位で行うこともすごく大事なこと。いわゆるスマートフォンなどの端末を使ったキャッシュレス決済を中心に行うということ。キャッシュレス利用していますか。
キャッシュレスを使うことに抵抗がない方もいるとは思いますが、抵抗のある年代の方、個人もいらっしゃいますよね。もし、使いづらいとなった場合に、そうなるとチケットを用意しないといけない、あるいは違う手法で物価高騰対策をやらないといけない。となりますと、そこにかかるコストというのが結構大きいということです。すると結果的に、物価対策としての製作予算としての効果が薄れますよね。紙にするといったことをデジタルにすることで、より経済効果を高めていきたいという考え方です。手法はキャッシュレス決済の1本でいくという形です。今回は、使った金額の20%がポイントになるという仕組みです。
PayPayも対象になっています。PayPayの場合、1,000円購入すると20%ですから、200円分のポイントが付くという形になります。ポイントは貯めていますか。ポイントの還元もするということです。そんな形でやっていきたいと。
期間は11月の1か月。今部長も申し上げましたが、売上が落ち込むとき。昔は2月や8月と言いましたけど、今11月が落ち込むそうです。11月の売上が落ち込むとき、そういうニーズに対して応えていきましょうという形であります。こういったことは商工団体とも連携して、ご要望にお応えする形で対応していく。こういう考えでございます。
Q7:記者
ここでどうしても問題になってしまうのが、そういった電子ポイントを使えない方とか、普段からスマホで電子決済されない方がいらっしゃると思います。それから私みたいに恩恵を受けてしまう方と、実際に恩恵を受けられない方も出てくると思います。そこに対する公費の投入というのは・・・難しい部分があるのかと思いますけど、市長はどのようにお考えですか。
A7:市長
これまでもキャッシュレス的なものを適宜、キャッシュレスやってきましたよね。以前の取り組みの中では、例えばお子さんが、その方の親御さんの端末を用いてセッティングをして行う。ということも、行いうることではないですか。今回、何が目的かというふうになった場合に、どなた様の生活支援もということも当然ありますが、できうるわけですけども。しかしながら、どっちの経済効果を高めていくかと言った場合においては、事業者支援によって回るお金を大きくしていこうという形です。PayPayのほかにもいくつか使っていますか。
それぞれに満額がありますけれども、d払い満額、PayPay満額、auPAY満額というように、掛ける1掛ける2掛ける3というふうになっていきます。キャッシュレスを複数使うことによって、より効果的なものになっていくということで、やっていきたいというふうに思っています。ワクワクし始めましたか。思いを深めていただいて…お仲間にも吹聴願いますね。
ここで浅間病院事務長からの発言がありますので、お願いします。
:浅間総合病院事務長
先ほど病院の決算関係で答弁いたしましたが、補足させていただきます。先ほどの数字は収益から費用を差し引いた金額でありまして、損益計算書による6年度の決算では、8,636万円の純損失、赤字ということでございます。5年度が、4億1,800万円でありますから、対前年度と比べますと、3億3,000万円ほど赤字を圧縮しているということでございます。
(2)その他
Q8:記者
4月に市長選と市議選があり、6月議会が新しく改選後の初めての議会となりました。実際に新しい議員さんたちとの定例会があったわけですけども、新たな議会における印象、議会に対して変わった点、あるいは今後に期待する点など、議会に関しては何かございますか?
A8:市長
6月議会だけ見てではちょっとわからないとは思いますが。しかしながら質問のやり方が印象深いなという方もいらっしゃいます。まず質問して、第2質問、第3質問とありますが、第4質問ぐらいまでやった方もいらっしゃいます。あるいはまた質問をする中においてSNSを使うなど。世論調査とまでいくかはわかりませんが、アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込みや偏見)というものがありますが、「あなたの暮らしの中でアンコンシャス・バイアスを感じるシーンとはどういうものがありますか」という資料を作って、SNSでデータを取って、そこから質問されるというケースもありました。それぞれの特徴ある質問をされていらっしゃるなと感じています。そしてそれがキャリアのある議員さんを今後触発していく。平たく言うと刺激する。というようなことが起こってくるだろうというふうに、私の経験上、思っています。今後、活発な議論がなされていくだろうと思います。
また、ちょっと濃淡があるなと思うのは、今回の新人の方の中においても、SNSを駆使している方と、ちょっと距離のある方があるということを感じます。若い方がSNSなどを頻繁に使って、上の方が乏しい。という傾向ではなくて、個々によるということです。やり方はそれぞれですから。SNSというのは新しい手法だけれども、唯一の手法じゃない、それはそんなに気にはしていませんが、個々の違いを感じています。様々な催しなどをみても、足を運ばれる方は積極的に足を運ばれる方が多くなってきている。そういったものが今後の活動に生かされるのではないかなというふうに思っています。議論をしていく中においても重要です。私も議会出身ですので思うことに、「知らないことを聞いているうちは質問にならない」ということ。ご自身が思っている、描いているものに社会を誘導していく。そのための手法としての質問だと思いますから、そういう意味では、知らないことを聞いているという水準からは比較的遠ざかっていると。より質問らしい質問になってきているのではと思います。これはよく一般的に地方議会で言われることに、「一般質問のような代表質問」「委員会質問のような一般質問」このようなことをよく言われます。そういったものが、今後より深い活動と議論の中で広がっていくのではないかと。そんなことを期待しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ