更新日:2024年12月26日
本展示会「広報取材班 推し作品展示します」は、広報佐久取材班と佐久市立近代美術館が協力して開催します。
佐久市の広報紙《Saku LIFE》は、広報佐久の取材班が地域や季節の話題を独自取材し、巻頭特集として毎月お届けしています。令和7年1月号の特集は、佐久市立近代美術館の話題を掲載しています。
今回の巻頭特集の目的は、「市民の皆さんが美術を楽しむため佐久市立近代美術館に来館する」ことです。巻頭特集の企画会議において、広報佐久取材班と佐久市立近代美術館は共通の認識に立った話し合いから、「取材班が推薦する作品」を展示することになりました。
本展示会は、佐久市立近代美術館収蔵の美術作品から、広報佐久取材班が市民の皆さんに見てもらいたいと思った作品を、同取材班の推薦文とともに展示しています。
《Saku LIFE》に掲載した作品も展示しています。
多くの市民の皆さんに鑑賞してもらう展示会です。どうぞ楽しんでご鑑賞ください。
展示会会期
会期中の休館日
開館時間
会場
主催
観覧 無料
近代日本で最も著名な日本画家の一人、横山大観の名前は取材班でも知っています。大観の描いた作品が佐久市立近代美術館にも収蔵されていると聞いて驚きました。みなさん、一緒に実物をみてみましょう。 (取材班)
横山大観(よこやまたいかん・1868-1958)
茨城県生まれ。日本画家。明治11年(1878)に一家で上京。明治21年(1888)、母方の姓をついで横山となった。明治22年(1889)、新設の東京美術学校に入学し橋本雅邦に学んだ。明治29年(1896)、東京美術学校助教授となるが、明治31年(1898)の校長岡倉天心排斥の内紛に殉じて同年辞職、日本美術院の創立に参加した。理想主義を掲げ、自然を純化するなど新しい日本画創造に尽力した。明治36年(1903)から約2年、海外に視察。大正3年(1914)には日本美術院を再興した。近代日本画界の第一人者であった。昭和12年(1937)文化勲章受章。 (佐久市立近代美術館)
《林亭の朝》1930年制作、147.5×79.5×2扇、紙本墨画淡彩
松林に一軒の離れ屋が建っている。朝靄の中に、離れへと続く回廊も見え隠れする。それ以外あまり描かれていないが、余白に淡く刷いた金泥や黒い鳥の演出効果は高く、鑑賞者の関心は左方向へ飛んでいく鳥に伴って画中に引き込まれていく。 (佐久市立近代美術館)
縁起の良い絵を飾り正月をお祝いしたい、と思い作品を探していたら、美術館スタッフが富士山の絵を教えてくれました。奥村土牛の《富士》です。絵にまつわるよもやま話もあって、今回の企画展示にピッタリな作品だと思いました。広報佐久1月号の表紙にも掲載しました。ご覧ください。 (取材班)
奥村土牛(おくむらとぎゅう・1889-1990)
東京生まれ。日本画家。16歳で日本画家・梶田判古に入門し、師の没後は兄弟子・小林古径のもとで研鑽を積んだ。昭和2年(1927)38歳で再興第14回院展に初入選。40代年半ばから高い評価を得る。戦後は《那智》(山種美術館蔵)や《鳴門》(山種美術館蔵)など代表作を次々と発表した。平成2年(1990)に101歳で没するまで、生涯を通じて制作に取り組んだ。
土牛は昭和20年(1945)5月に臼田町(現・長野県佐久市臼田)へ疎開している。昭和22年(1947)には近隣の穂積村(現・長野県南佐久郡佐久穂町)に移り、東京に戻るまで4年間を過ごした。平成2年(1990)には八千穂村(現・長野県南佐久郡佐久穂町)に「奥村土牛記念美術館」が開館するなど、佐久地域とゆかりが深い。昭和37年(1962)文化勲章受章。 (佐久市立近代美術館)
《富士》1976年制作、65.8×81.7cm、紙本彩色
土牛は多くの富士山を描いている。本作の富士について述べている言葉を紹介する。
「この富士は、東海道線の富士駅の辺りからのものである。前夜、駅近くの旅館に一泊、早めにやすんで夜明けを待った私は、翌朝は空が白み始めるのももどかしい気持で、旅館を抜け出した。幸い、この日は、願ってもない上天気で、富士は闇の中から白い稜線をくっきりと現し始め、そして見る見る鮮やかな色彩に染まっていった。それは、実に壮厳な眺めだった。」(曙 奥村土牛『新美術新聞』(株)美術年鑑社、1977年)
美術年鑑社初代社長だった油井一二から十二支の作品を依頼され、昭和51年(1976)の辰に続き描いた作品で、蛇が描けなかったため朝日に照らされた富士となった。昭和52年(1977)巳年の『新美術新聞』1月20日に、《己》と書かれた色紙と共に掲載された。 (佐久市立近代美術館)
《己》1977年制作、27.3×12.3cm、色紙・墨
昭和52年(1977)1月20日号の『新美術新聞』掲載のために制作された作品と思われる。良寛風の書体で「己」と書かれている。この年の干支は「丁巳」であったので「巳」と書きたかったのかもしれない、と考えるとまた違った興味がそそられる。 (佐久市立近代美術館)
佐久市立近代美術館には、有名でファンも多い武者小路実篤の作品も収蔵されています。コレクターの油井一二が実篤に私淑していたからだそうです。わかりやすくて、親しみが持てる、そして正月にふさわしい縁起の良い絵を選びました。 (取材班)
武者小路実篤(むしゃこうじさねあつ・1885-1976)
東京都生まれ。小説家、画家として著名で、戯曲、詩、評論など著した。明治43年(1910)に志賀直哉、有島武郎、有島生馬らと雑誌『白樺』を創刊(関東大災を機に終刊)し、以後60年余にわたって文学活動を続けた。大正7年(1918)に理想社会の実現に向け、宮崎県で「新しき村」を、昭和14年(1939)には埼玉県で新「新しき村」を創設した。昭和26年(1951)文化勲章受章。 (佐久市立近代美術館)
《達磨》1958年制作、44.8×50.6cm、絹本墨書淡彩
実篤は40歳頃から絵画を描き始めている。和紙に薄めの墨と淡い色彩で、身の回りの物を描き自書を添えた。平易な言葉で画風と同じように柔らかな書体で書かれてはいるが、古典や慣用句などから引用されている言葉もある。
達磨は中国禅宗の始祖とされている僧で、多くの人は達磨大師の姿をまねた張り子人形を思い浮かべる。倒してもすぐ起き上がるように作られていることから「七転八起」という言葉がよく似合う。実篤はこの四文字熟語を、新約聖書からの引用文とあわせて創作した文を「画賛」として書いた。
「そのとき、ペトロがイエスのところに来て言った。『主よ、兄弟がわたしに対して罪を犯したなら、何回赦すべきでしょうか。七回までですか。』イエスは言われた。『あなたに言っておく。七回どころか七の七十倍までも赦しなさい。」(新共同約 新約聖書『マタイによる福音書18章21-22節』一般財団法人日本聖書協会)
(油井一二の依頼により制作された本作は和紙ではなく絹に描かれている) (佐久市立近代美術館)
佐久市立近代美術館への取材で、収蔵する作品はお金にするといくらくらいの価値があるか尋ねたところ、美術館スタッフが「お金で評価しませんが、作品を寄付してくれた人からの申告額はわかります」といって、3億5千万円の作品を教えてくれました。3億越えの絵が気になるので、実際に展示してもらいます。 (取材班)
平山郁夫(ひらやまいくお・1930-2009)
広島県生まれ、日本画家。昭和20年(1945)に広島市内で被爆した。昭和22年(1947)に東京美術学校(現・東京藝術大学)日本画科に入学、卒業後は同校日本画科の副手となり、主任教授だった前田青邨に師事した。仏教やシルクロードを題材とした作品を制作したことで知られる。平成10年(1998)文化勲章受章。 (佐久市立近代美術館)
《日光東照宮》1986年制作、99.7×65.0cm、紙本彩色
《浅間山(挿絵)》1968年制作、33.0×48.2cm、紙・色鉛筆
平山郁夫は幾度か佐久の地を訪れている。《浅間山》を描いた昭和43年(1968)は、油井一二に招かれ、佐久市出身の詩人三石勝五郎の著書「摂政の宮 行啓地・信濃閼伽流山」の挿画を制作するため滞在した。
その後、昭和58年(1983)6月26日、当美術館の開館記念式典に出席のため佐久市を訪れている。翌年4月には、平山の生誕地広島県瀬戸田町の小学校の学外での課外活動の恩師(当時瀬戸田高等女学校教師・佐久市出身)と、40数年ぶりに当美術館において再会するという出来事もあった。
平成元年(1989)4月、佐久市は平山に佐久市名誉市民章を授与し、その功績を顕彰した。今回の展示では、佐久ゆかりの作品と、1989年制作《日光東照宮》を楽しんでください。 (佐久市立近代美術館)
コレクター油井一二は、日本画ばかりでなく、日本の美術界の各分野の作品を収集しました。そこで、油彩画からも、著名な作家が制作したお正月にふさわしい作品を選定しました。《初日》は元日の朝の太陽のこと。昭和51年(1976)1月1日発行の『新美術新聞』に掲載された作品です。お正月のいま、鑑賞してもらうしかないですよね。 (取材班)
小絲 源太郎(こいとげんたろう・1887-1978)
東京都生まれ。洋画家。17歳の時、洋画家・藤島武二の作品に感動して画家を志し、明治38年(1905)、藤島の指導する白馬会駒込研究所に入る。明治39年(1906)東京美術学校(現・東京藝術大学)金工科に入学。卒業後改めて西洋画科に入るが、病により中退する。在学中の明治43年(1910)第4回文展に初入選し、以来、帝展、日展へ出品した。昭和40年(1965)文化勲章受章。 (佐久市立近代美術館)
《初日(はつひ)》1975年制作、22.5×28.0cm、キャンパス・油彩
昭和10年(1935)頃から筆の跡がおおまかな作品を制作するようになった。晩年制作の本作は、シンメトリーな構図で、元日に水平線から昇ったばかりの太陽が薄雲の向こう側から力強い光線を放っている様子が、縦と横の太い筆跡で強調され、海面の波を表現したリズミカルな筆触と共に鑑賞者に迫ってくる。 (佐久市立近代美術館)
コレクター油井一二は、日本画ばかりでなく、日本の美術界の各分野の作品を収集しました。縁起がいいとされる富士山を描いた作品を、油彩画からも選びました。画家も著名な牛島憲之とのこと。うす塗りの色彩がさわやかですが、力強さも感じるしっかりとした絵画です。 (取材班)
牛島憲之(うしじまのりゆき・1900-1997)
熊本県熊本市生まれ。昭和2年(1927)東京美術学校(現東京藝術大学)西洋画科卒業。以後帝展・日展などで受賞を重ねたが、昭和24年(1949)に研究の場として立軌会を結成してからは、在来の公募展とは距離を置いた。昭和29年(1954)から東京藝術大学講師(後に教授)。昭和58年(1983)文化勲章受章。牛島は生涯、柔らかいタッチの風景画を描き続けた。 (佐久市立近代美術館)
《黎明富士》1987年制作、33.5×45.5cm、キャンバス・油彩
《巳》1989年、27.3×24.3cm、色紙・墨
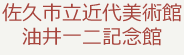
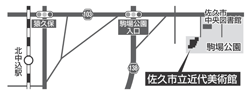
毎週月曜日(休日の場合は開館)
展示替え期間(不定期)
年末年始期間(12月29日~1月3日)
ほか臨時休館することがあります。
午前9時30分~午後5時