更新日:2024年9月15日
当館の所蔵する作品の中から、佐久地域にゆかりの作家たちの作品を選んで展示します。ここでの佐久地域とは、現在の佐久広域連合*の範囲に当たります。
選出した作家のうち、14名は佐久地域出身の作家たちです。
また昭和20年(1945)頃には、東京の戦火を避けて佐久の地に疎開し、地域の人々と交流をもち作品を残した作家たちがいました。有島 生馬、奥村土牛、加藤陽、源川雪らは、そうした作家です。
田崎廣助は、軽井沢町に別荘兼アトリエを持ち、没後、町内に財団法人田崎美術館が開館しました。
安原喜明は東京の目黒に生まれた陶芸家ですが、遺族によると、祖先は佐久市安原の地と縁が深いとのことです。
それぞれの在り方で佐久地域と関りを持った、多彩な作家たちの作品をお楽しみください。
*広域連合:区市町村の区域を超える広域行政のための特別地方公共団体で、佐久広域連合は旧北佐久郡(北御牧村を除く)と旧南佐久郡の地域に当たり、現在の佐久市、小諸市、北佐久郡(軽井沢町、御代田町、立科町)、南佐久郡(佐久穂町、小海町、北相木村、南相木村、南牧村、川上村)の各自治体により構成されている。
展覧会期
会期中の休館日
開館時間
会場
観覧料
(同時開催の「牧野一泉 日本画展 ―人型の向こう側―」を含めすべての展示を観覧できます)
おかむらまさこ・安政5年-昭和11年(1858-1936)・享年78歳・画作者
岩村田藩士山室直高の子として江戸に生まれ岩村田に育つ。明治7年(1874)上京。明治9年(1876)工部美術学校に入学、第1期生。アントニオ・フォンタネージ*に洋画を学ぶ。明治11年(1878)退校。明治13年(1880)岡村竹四郎と結婚。石版印刷業信陽堂を始め、政子は主に原画制作を担当した。関東大震災で印刷業は廃業。
*アントニオ・フォンタネージ(Antonio Fontanesi・1818-1882):イタリアの画家。明治9年(1976)に日本で開校した工部美術学校で洋画を指導した。
こうづこうじん・明治22年-昭和53年(1889-1978)・享年88歳・洋画家
北佐久郡志賀村(現・佐久市志賀)生まれ。明治37年(1906)頃丸山晩霞に師事。明治40年(1907)から明治45年(1907-1912)まで東京美術学校西洋画科に学ぶ。光風会展、文部省美術展覧会、帝国美術展覧会等に出品。大正9年(1920)農商務省商業美術研究生として渡欧。ロンドン チェルシィLLC美術学校、ロイヤルアカデミースクール、パリ アカデミージュリアンで学ぶ。大正11年(1922)イタリアから帰国。昭和3年(1928)官展*を離れ構造社絵画部創設。昭和7年(1932)口スアンゼルス第10回オリンピック大会芸術競技役員として渡米。昭和14年(1939)緑巷会を創設し主宰する。昭和19年(1944)志賀村へ疎開。昭和22年(1947)東京に転居。昭和25年(1950)、主宰団体を創芸協会と改称。昭和32年(1957)創芸協会を第一美術協会に合併、第一美術協会名誉会員となる。長野県展審査員など務めた。
*官展:民間の美術団体が行う美術展に対して、政府(官)が主催する美術展覧会の通称。明治40年(1907)の文部省美術展覧会に始まり、帝国美術院展覧会、文部省美術展覧会、日本美術展覧会と名称を変えながら昭和23年(1948) まで続いた。昭和24年(1949)から日本芸術院と日展運営会の共同主催となり、昭和33年(1958)民間団体である「社団法人日展」(当時) の運営となった。
のむらしょうざぶろう・明治37年-平成3年(1904-1991)・享年87歳・洋画家
南佐久郡野沢町三塚(現・佐久市三塚)生まれ、大正13年(1924)長野県立野沢中学校卒業後、太平洋画会研究所入所。大正14年-昭和3年(1925-1928)東京高等師範学校図画手工専修科。新潟県、和歌山県、静岡県、愛媛県で美術を教える。昭和20年(1945)故郷に疎開。昭和21年(1946)松山市に転居。愛媛大学に勤務、助教授、後に教授となる。昭和29年(1954)から二科展*に出品、昭和46年(1971)二科会会員。
*二科展:日本の美術団体のひとつ公益社団法人二科会が開催する美術展覧会。現在は毎年、絵画部・彫刻部・デザイン部・写真部からなる展覧会を開催している。
おぎはらこういち・明治42年-昭和52年(1909-1979)・享年70歳・洋画家
南佐久郡野沢町(現・佐久市取出町)に生まれる。昭和2年(1927)長野県立野沢中学校卒。東京美術学校で藤島武二の指導を受け、昭和9年(1934)卒業。昭和13年(1938)から長野県立野沢中学などで美術を教えた。神津港人に師事。昭和22年(1947)第3回全信州美術展出品。日本美術展覧会入選。第1回長野県展から入選。緑巷会入選。昭和29年(1954)一水会会員。
ひなたゆたか・大正元年-昭和49年(1912-1974)・享年61歳・洋画家
南佐久郡青沼村(現・佐久市入沢)生まれ、昭和6年(1931)長野県立野沢中学校卒、上京し川端画学校に学ぶ。昭和13年(1938)東京美術学校油画科卒。昭和15年(1940)長野県立木曽中学校と高等女学校等で教諭を勤める。昭和17年(1942)退職。昭和21年(1946)から全信州美術展、国展*、長野県展出品(第5回以降審查員)。昭和24年(1949)国画会会員。昭和31年-昭和33年(1956-1958)渡仏。
*国展:国画会が運営する美術作品公募展。現在は絵画部、版画部、彫刻部、工芸部、写真部からなる。
よしのじゅん・大正11年-平成30年(1922-2018)・享年95歳・洋画家・本名純夫
南佐久郡臼田町(現・佐久市臼田)生まれ。昭和14年(1939)長野県立野沢中学校卒。昭和17年(1942)東京高等師範学校芸術学科入学、昭和23年(1948)同校研究科絵画専攻卒。高校美術教師を経て、昭和28年(1953)から東京教育大学芸術学科絵画研究室で助手となる。昭和60(1985)年筑波大学芸術学系教授定年退官。
宮本三郎の勧めで二紀展*に出品。会員、理事を経て、晩年二紀会副理事長を勤めた。
初期にアンフォルメルの影響を受けた作品を発表していたが、昭和40年(1965)の渡欧でロマネスク美術に衝撃を受け、重厚なマチエールとプリミティブで詩的なフォルムの作品へと変わった。
*二紀展:一般社団法人二紀会が開催する美術作品公募展。昭和22年(1947)、宮本三郎を含む9名の作家により、「美術の第二の紀元を画する」の意図のもと前身の第二紀会が創立された。
さくらいひろし・昭和6年-(1931-)・洋画家
南佐久郡臼田町(現・佐久市臼田)生まれ。昭和25年(1950)長野県野沢北高等学校卒。昭和30年(1955)東京教育大学芸術学科卒。在学中より独立美術協会展*に出品。長野県展に出品、昭和46年(1971)から審査員。武蔵野美術大学、女子美術大学の講師をしながら制作を続ける。後に武蔵野美術大学教授。昭和42年(1967)独立美術協会会員。古いトランク、フライパンと目だま焼き、軋んだベットなど身のまわりのものを題材に描き、黒を基調とした重厚な画面で定評がある。
*独立美術協会展:昭和5年(1930)創立の美術団体独立美術協会が開催した美術作品公募展。現在、展覧会名称は独立展といい、令和6年(2024)で91回を数える。
展示作品リスト がダウンロードできます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
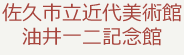
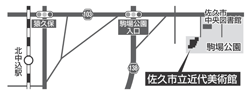
毎週月曜日(休日の場合は開館)
展示替え期間(不定期)
年末年始期間(12月29日~1月3日)
ほか臨時休館することがあります。
午前9時30分~午後5時